
『悪の華(Les Fleurs du mal)』は1857年に裁判にかけられ、社会の風紀を乱すものとして、100編の内の6編の詩の削除が命じられた。
その後、ボードレールは、1861年に『悪の華』第2版を出版するにあたり、新たに32編の詩を加えると同時に、「パリ情景(Tableaux parisiens)」と名付けた新たな章を作り、1857年の初版とは異なる様相を示す詩集とした。
「風景(Paysage)」は、その新たな章である「パリ情景」の冒頭に置かれ、ボードレールの描き出す都市風景がどのように生成されるのかを示す役割を果たしている。
別の言い方をすると、この詩は、「私(Je)」と名乗る詩人が、パリの情景をテーマとする詩を「創作する(composer)」姿を描いているのだといえる。
まず、最初の8詩行を読んでみよう。
Je veux, pour composer chastement mes églogues,
Coucher auprès du ciel, comme les astrologues,
Et, voisin des clochers écouter en rêvant
Leurs hymnes solennels emportés par le vent.
Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde,
Je verrai l’atelier qui chante et qui bavarde;
Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité,
Et les grands ciels qui font rêver d’éternité.
私が望むのは、私の田園詩を清らかに創作するために、
空の傍らに横たわること、天文学者のように。
そして、鐘楼の横で、夢を見ながら、耳を傾けること、
風に運ばれる堂々とした賛歌に。
両手を顎につき、屋根裏部屋の上から、
私は見るだろう、歌を歌い、おしゃべりをする工房を、
煙突を、鐘楼を、それらは都市のマストだ、
そして、大空を、それらは永遠を夢想させてくれる。
第1−4詩行では、詩作に向かう姿勢が喚起される。
まず最初に、「私」の創作するものが「私の田園詩(mes églogues)」と言われる。
田園詩とは、一般的に、自然の風景を背景にした牧歌的な詩。そこでは、しばしば、羊飼いと少女の純粋な愛の語らいが歌われる。
それに対して、現代の詩人は、背景を田園から都市に移行し、都市の風景を描く。
そして、その際には、官能性の強い刺戟的な物語や描写ではなく、田園詩に倣い、「清らかな(chastement)」語り口を心掛ける。
そうした詩を書くために「私」が望むのは2つ。
1)空の傍らに(auprès du ciel)、横たわる(coucher)こと。
その姿を「天文学者(les astrologues)」になぞらえるとしたら、どのように理解したらいいのだろう?
天文学者は天空の星々を観察し、地上の様々な出来事の予測をし、人間の運命を読み説いたりする。
それと同様に、詩人も、都市の様々な兆候を読み取り、解読する役割を担っているのだと考えられる。
2)鐘楼の近く(voisin des clochers)で、風(le vent)の音を聴く(écouter)こと。
ただし、耳を澄ませて外部の音を客観的に聞くのではなく、夢見ながら(en rêvant)であることに注目しなければならない。
夢心地でいるからこそ、、鐘楼(les clochers)の近くを吹き抜ける風の音が、鐘楼の奏でる堂々とした賛歌(Leurs hymnes solennels)として聞こえる。
。。。。。
第5−8詩行になると、「私」と都市の状況が描き出される。
ここで注意しなければならないのは、« Je verrai » と動詞の時制が単純未来に置かれ、実際に目にしている風景ではないこと。
言い換えると、全ては想像の世界で繰り広げられる出来事なのだ。

その世界の中で、「私」は、屋根裏部屋(ma mansarde)の中で、両手を顎に乗せ(Les deux mains au menton)、地上を眺める。
その姿は、シャルル・メリヨンの銅版画「吸血鬼(Le Stryge)」を連想させるとしばしば指摘される。
そして、こうした姿をして、眼下に見下ろす先には、人々が忙しく働く工房(l’atelier)や、煙突の管(les tuyaux)や教会の鐘楼(les clochers)が見えてくる。


そうした中、詩人は、街を海にたとえ、家々の上に立ち並ぶ煙突や教会の鐘楼を船のマストだと言う。
そして、海(=街並み)の上に広がる大空を見上げ、「永遠(éternité)」を夢見る。
こんな風にして、屋根裏部屋の窓からはるか下方を見下ろし、人々が活動する家々が立ち並ぶパリの街並みを海とそこに浮かぶ船のように思い描く。
その時、現実の都市の情景が、そのままの姿で、永遠を夢見させるものに変貌する。
そのように考えると、この8行の詩節でボードレールが読者に伝えようとしたのは、時間とともに消え去る現実の対象を捉えながら、そこに永遠の相を付与する、彼の「モデルニテ(現代性)の美学」だといえる。
その美学は、「現代生活の画家」という美術批評の中で、次のように定義されている。
美を構成する要素の一つは、永遠で不変なもの。その数量を決定することは極度に難しい。もう一つの要素は相対的で、状況に依存し、もしこう言ってよければ、代わる代わるに、あるいは一体化して、時代、流行、道徳、情熱になることがあるだろう。(中略)
こうした芸術の二重性は、人間の二重性の避けがたい結果である。永遠に存続する部分は芸術の魂であり、変化する要素はその肉体だと考えるといい。
9詩行から第2詩節が始まり、20行目までは視覚に訴えかけるものが次々に描かれる。
その際にも、実際に見えるのではなく、未来のこととして言及されることは、これまでと同様である。
まず、9-12詩行を辿っていこう。
II est doux, à travers les brumes, de voir naître
L’étoile dans l’azur, la lampe à la fenêtre
Les fleuves de charbon monter au firmament
Et la lune verser son pâle enchantement.
気持ちのいいのは、霧を通して、見えること、
窓辺にランプが置かれ、青空の中にあの星が生まれるのを、
石炭の大河が大空に上るのを、
月が青白い魔性の魅力を注ぐのを。
霧(les brumes)で覆われた街並み。その中で、屋根裏部屋の窓にランプを置き、外の景色を眺めている場面を空想する。
その時、見えてくるように思われる3つ示される。
1)青空(l’azur)の中に星(l’étoile)が生まれる(naître)。
この光景は、青空という昼の時間に、星という夜の事象が重なることで、非現実の場面を思わせる。
2)石炭(charbon)の大きな河(les fleuves)が幾本も大空(le firmament)に上る(monter)。
工場の煙突から立ち上る煙を大河と表現することで、先に出てきた海のイメージと繋がる。
3)月(la lune)が、青白い魔性の魅力(le pâle enchantement)を注ぐ(verser)。
フランスでは、太陽は黄色で、月は白で描かれる。
そこで、月の白い光が夜の街を照らす光景が、なにやら神秘的で、魔法にかけられ、現実ではないように感じられる。
これらの三つの情景は、現実でありながら、夢想的な姿として浮かび上がってくる。
第13-20詩行でも、動詞は単純未来で活用され、空想の世界が作り出される。
Je verrai les printemps, les étés, les automnes;
Et quand viendra l’hiver aux neiges monotones,
Je fermerai partout portières et volets
Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais.
Alors je rêverai des horizons bleuâtres,
Des jardins, des jets d’eau pleurant dans les albâtres,
Des baisers, des oiseaux chantant soir et matin,
Et tout ce que l’Idylle a de plus enfantin.
私は見るだろう、春を、夏を、秋を。
そして、単調な雪が降る冬がやって来る時、
閉じるだろう、いたるところで、扉や鎧戸を、
夜の間に建てるために、妖精の住む宮殿を。
そして、夢見るだろう、青っぽい地平線を、
庭を、雪花石膏の中で涙する噴水を、
口づけを、朝に夕に歌を歌う鳥たちを、
そして、田園詩の持つ最も子供っぽいもの全てを。

最初に四季の移り変わりが思い出される。しかし、それは時間の流れを示すためではなく、単調な雪(les neiges monotones)の冬(l’hiver)に至るための過程だと考えられる。
その冬になると、扉(portières)や鎧戸(volets)が閉じられ、全ては動きを止め、夜が訪れる。そこで建てられる宮殿(les palais)が妖精(fée)を思わせ夢幻的(féeriques)なのは、夜が永遠に続くことを暗示する。
「私」が実際にいるのは屋根裏部屋だが、空想の中では宮殿の中にいる。そんな状態の中で、夢見ることになる「地平線(des horizons)」や「庭(des jardins)」などが列挙される。
その中でも、噴水(des jets d’eau)が雪花石膏の中で涙する(pleurant dans les albâtres)姿や、朝に夕に歌を歌う鳥たち(des oiseaux chantant soir et matin)は、妖精の住む宮殿へと読者を導いていく。
そして、「私」の想像によって作り上げられる世界の全てのものは、田園詩(l’idylle)で歌われる子供っぽい(enfantin)ものに属し、「私の田園詩を清らかに構成する(composer chastement mes églogues)」という冒頭の詩句と対応する。
その全体を通して見ると、「私は見るだろう(je verrai)」から「私は夢見るだろう(je rêverai)」への移行は、未来のことを想像するという点では共通している。
しかし、その過程で、意識が現実的な知覚を離れ、夢幻的な世界に入っていく。そのことは、現実からの隔たりがさらに大きくなったことをはっきりと示している。
そこでは、屋根裏部屋は姿を消し、妖精の住む宮殿が出現する。
第21詩行の冒頭では、そうした夢幻世界の魔法を解くかのように、ボードレールはあえて「暴動(l’Émeute)」という言葉を使うことで、一瞬の間ではあるが現実へと意識を向けさせる。
L’Émeute, tempêtant vainement à ma vitre,
Ne fera pas lever mon front de mon pupitre;
Car je serai plongé dans cette volupté
D’évoquer le Printemps avec ma volonté,
De tirer un soleil de mon cœur, et de faire
De mes pensers brûlants une tiède atmosphère.
「暴動」が、ガラス窓に嵐のように吹いてきても無駄、
私は、書面台から顔を上げることはないだろう。
なぜなら、あの官能に浸るだろうから、
私の意志によって「春」を呼び出す官能、
私の心から太陽を引き出す官能、そして、
燃える上がる思考を生暖かい雰囲気に変える官能に。

« l’Émeute(暴動)»という言葉の先頭が大文字に置かれているが、ここでは何か一つの事件、例えば、1848年の2月革命とか、それに続く6月の暴動を指し示すわけではなく、現実の世界に起こりうる暴動というものを提示するためだと考えられる。
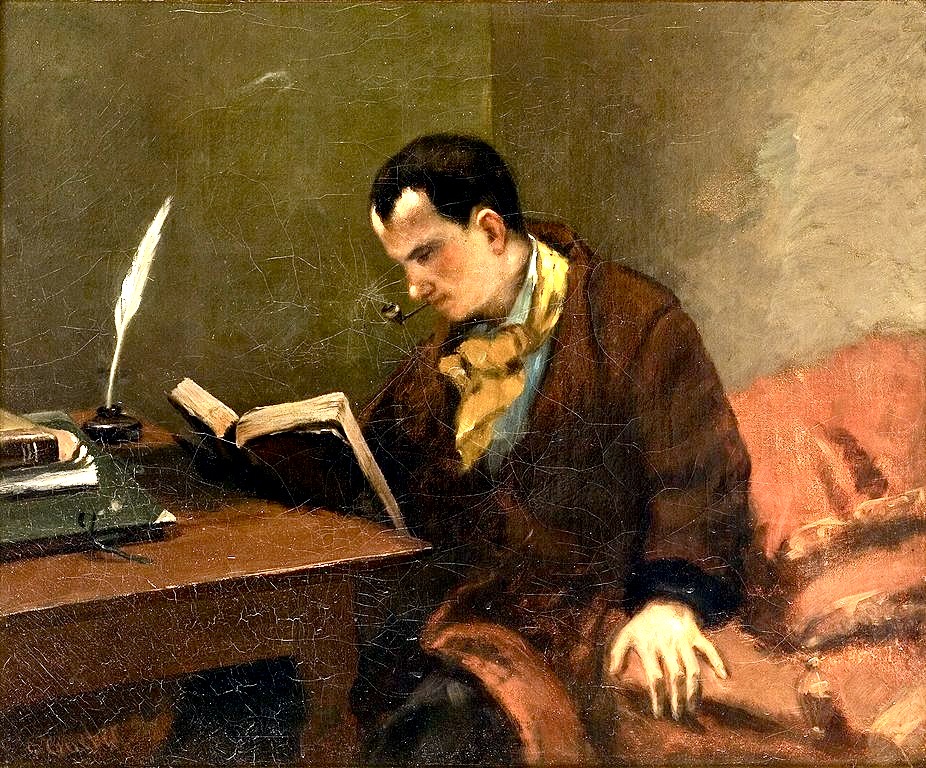
そうした暴動が外の世界で吹き荒れる(tempêtant)としても、「私」は書見台(ma pupitre)から顔を上げない。
その姿勢は、詩を書くのを止めることも、そこで作り上げられる想像世界から離れることもない、ということを意味している。
そして、その理由が「官能(volupté)」という言葉によって示される。
一般的に言えば、官能とは肉体的な刺戟によると考えられるが、この詩ではこれまでにも、「清らかに(chastement)」や「子供っぽさ(enfantin)」という言葉に代表されるように、外部から五感に及ぼされる刺戟によってもたらされる官能性とは違う方向に向かってきた。
ここで言われる官能の中身として、3つのことが示される。
1)意志(ma volonté)の力によって「春(le Printemps)」を思い起こさせる。
先に四季に言及された際には、単調な雪の降る冬に行き着いた。しかし、ここでは「春(le Printemps)」が呼び起こされる。
綴り字の最初が大文字にされたその春は、通り過ぎる時間に属するのではなく、永遠の春と考えていいだろう。
そして、それを可能にするのは、私の意志(volonté)。
ここまで未来時制で語られてきた想像世界は、インスピレーションによるのではなく、意志の力を発揮し、細部まで構成したものであることを暗示している。
2)私の心(mon cœur)から太陽(un soleil)を引き出す(tirer)。
太陽はプラトンにおけるイデアを指すものと考えると、心によって永遠の世界を作りだすことを暗示する。
3)燃える上がる思考(mes pensers brûlants)を生暖かい雰囲気(une tiède atmosphère)に変える。
時間に永遠性を付与するためには、意志と同様に思考(mes pensers)が必要になる。
そこでは、思考が「燃え上がる(brûlants)」ように働くのではなく、「生温かな(tiède)」状態であると暗示する。
「私」は、書面台(mon pupitre)に向き合い、これらを行う官能に浸りながら、詩作を続けていくことになるだろう。
「パリ情景」を構成する詩篇は、「風景」で提示されたボードレールの美学に基づいているのだと考えることできる。
1857年の裁判の際に、6編の詩が社会道徳を乱すという理由で削除を命じられた。実際、それらの詩は、激しい肉体的な官能の刺戟を伴う詩句を含んでいる。
それに対して、1861年の『悪の華』第2版で新しく作られた「パリ情景」の章に含まれる詩篇は、検事から告発されるような詩句を含まない。
その意味では、自然の代わりに都市を背景とし、「清らかに(chastement)」に創作した「田園詩」だといえる。
「白鳥(Le Cygne)」「7人の老人たち(Les Sept Vieillads)」「小さな老婆たち(Les Petites Vieilles)」「通り過ぎる女(ひと)へ(À une passante)」「夕べの黄昏(Le Crépuscule du soir)」などに目を通せば、それらの詩篇が、「穏やかな官能」に基づいていることが理解できるだろう。
従って、「風景(Paysage)」は、「パリ情景」詩篇全体の序文としての役割を果たしているといえる。
