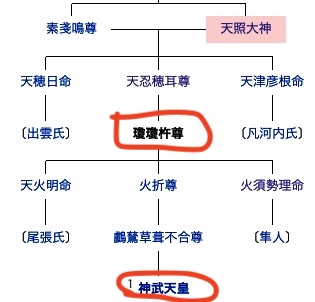現代の日本では、「言葉にしなければ自分の意志を相手に伝えられない」と言われることが多い。コミュニケーションが苦手な人の特徴として、「自分の意見をうまく言語化できない」といったことも挙げられる。
しかし一方で、「言わぬが花」という考え方や、「言わなくても分かる関係」が親密さの一つの指標になると感じられる場合もある。
仏教に由来する「以心伝心」や「阿吽の呼吸」といった言葉が、今も日本文化の中に息づいていることも確かである。
こうした相反する言語観を同時に抱えている現代の日本人には、「言わなくてもこれくらい分かるだろう」と「言わなければ分からない」との間で齟齬が生じることがある。「そこまで言わなくてもいいのに」と思うこともあれば、「もっと言ってほしかった」と感じることもあるだろう。
こうした状況にいるとき、これまでの日本文化の伝統の中で、言葉がどのように考えられ、どのように使われ、何を表現してきたのかを知ることは、現代の私たちが言葉について考えるうえでも有用である。
ここではまず、私たちの文化の根底に流れる仏教や荘子の言語観を考察し、ついで、そうした考え方が日本においては和歌や俳句といった言語芸術によって、いかに具体的に表現されてきたかを見ていくことにしよう。
続きを読む