(3)「地獄とは”他者たち”」 — 『出口なし』

サルトルにとって、人間とは「自由であることを常に余儀なくされている」存在である。
その一方で、社会の中で常に他者と関係しながら生きざるをえないことも否定できない。
その両面性を考えると、人間は自由であるが、同時に、他者の視線を感じ、他者に裁かれる存在でもある。
A. 他者の視線
サルトルは、『存在と無』の他者存在について論じる部分で、恥ずかしさの感情を取り上げ、自意識と他者の存在の関係について論じている。
何か不器用だったり、下品な振る舞いをしたとする。すると、その行為が私に貼り付く。私はそれを判断することも、批判することもない。単にそれを生きるだけだ。その実現は、「私に対して」というやり方でなされる。しかし、突然、私は顔を上げる。誰かがそこにいて、私を見ていた。と、突然、自分の行為の下品さを理解し、恥ずかしさを感じる。(中略)他者は、私と私自身の間の必要不可欠な仲介者なのだ。私が自分を恥ずかしいと感じるのは、他者に対してそんな風に見えるようになのだ。
(ジャン・ポール・サルトル『存在と無』)
この一節は、サルトルの実存主義哲学の3つのポイントを教えてくれる。
a. 即自
「ある行為」について、判断も批判もなく、ただあるだけ。
その際、意識は問題にされず、物が物としてあり、それだけの状態。
哲学用語では「即自」と呼ばれ、物がそのまま存在することを指す。
b. 対自
「私」が、「その行為」を恥ずかしいと感じる。
実践した行為を意識し、自分に恥ずかしさを感じることは、「そう感じる私」と「その行為」の間に距離が生まれたことを示す。その距離のために、「私」は、行為に対して何らかの感覚を持ち、判断するようになる。
そうした状態は「対自」と呼ばれ、自分に対する意識の存在が確認される。
c. 対他
誰かがそこにいて、私を見ていた。と、突然、自分の行為の下品さを理解し、恥ずかしさを感じる。
この一節は、自分に対する意識が生成するのは、「私」を見ている誰か(=「他者」)の出現と同時であることを示している。
他者の視線が、私たちに自己意識を芽生えさせる。他者の視線のもたらす恥ずかしさが、私たちに恥ずかしいという感情をもたらす。私たちの恥ずかしいという感情は、他者にそのように見えるという思いと対応する。
そうした他者存在は「対他」と呼ばれる。
サルトルは、「現実(実際)に存在する」状態において、あらゆるものの関係は「偶発的」であり、それだからこそ、人間には「自由」があり、その自由を行使するように強いられるのだと主張する。
『蠅』では、母親殺しを実践した後、「ぼくは”ぼく”の行為を実行したんです。(中略)それこそがぼくの自由なのです」と口にするオレステスに焦点を当てられ、人間の自由がテーマとされた。
『出口なし』は、閉ざされた空間の中に閉じ込められた三人の登場人物が、互いに他者を裁き、他者に裁かれる芝居。人間の意識は自由であることを原則としながらも、他者の視線によって束縛されている状況を描き出す。
B. 『出口なし』 — 「私」と他者の相互性

日本語で「出口なし」と訳されることが多い” Huis clos “は、当事者ではない傍聴者の入廷が禁じられた密室の裁判、つまり「非公開審理」を意味する。
サルトルは、その裁判室を地獄とした。実際、カフェのボーイに導かれて入室する登場人物は、3人の死者たち。
最初に入ってくるのは、ジャーナリストで平和主義者を名乗るガルサン。二番目は、郵便局に勤める女性で、同性愛者のイネス。三番目は、上流階級に属する女性らしいエステル。
彼らは、地獄には罪人を罰するための拷問の道具があるはずだと思い、そのための道具や拷問する人間について口にするのだが、しかし、密室の中には彼らだけしかいない。
イネス
すぐにそれがばかげたことだってわかるでしょう。本当にばからしいったらないわ! 肉体の拷問はないんじゃないの? でも、私たちは地獄にいる。誰もこんなところに来ないわ。誰も。私たちだけが最後までここにいるの。そうじゃない? でも、一人ここにいない人がいる。それは拷問する人間。
ガルシア(小さな声で)
わかってるよ。
イネス
だったら、人員削減したのね。それだけ。お客さんが自分たちでその役をするの、共同組合のレストランみたいに。
エステル
何が言いたいの?
イネス
私たち一人一人が拷問する人間なのよ、他の二人にとってね。
(ジャン・ポール・サルトル『出口なし』)

イネスの最初の言葉は、この部屋での拷問は肉体に対して行われるものではなく、精神的なものであることを暗に示している。
彼女の最後の言葉が明らかにするのは、拷問する人間は彼ら自身だということ。3人の登場人物たちは、一方では拷問される側にいながら、他方では拷問する側にも立つ。
その関係は、「私が自分を恥ずかしいと感じるのは、他者に対してそんな風に見えるようになのだ」という、『存在と無』の言葉を思い出させる。
他者からの視線、言い換えると、自分が他の人にどのように見られているのかという意識が、「私」の自己意識を方向付ける。
そうした「私」と「他者」の関係は相互的なものであり、「私」が「他者」を見る視線は、「他者」の自己意識に影響を与え、同時に、「他者」の視線は、「私」に影響を与える。
3人は最初、生前に犯した行為を隠し、密室に偶然居合わせているといった様子をしている。しかし、会話が進む中で、密室裁判所で尋問を受けているかのように、地獄であるその部屋に連れてこられた罪状を告白させられていく。
ガルサンは、妻を苦しめるために、あえて浮気の現場を見せるようなことをする男であり、自分の信じる平和主義のために銃殺されたと最初は言っていたのだが、実は軍隊を脱走したために銃殺されたのだった。
イネスは男性を嫌悪する同性愛者で、従兄の妻フロランスを誘惑し、悲しみにとらわれた従兄は死を選択する。フロランスはそのことで罪の意識を深く抱き、イネスと二人で寝ている間にガスを部屋に充満させた、二人は窒息死したのだった。
エステルは、自分と関係を持った若い男との間に産まれた子供を殺害し、子供の父親を自殺させる。

密室の裁判は、二人が問いかけ、一人が告白する形で進む。そして、順番に、地獄の一室に閉じ込められる原因となった顛末を語る。その際、話を聞く二人の他者の存在が、行為を犯した人間に自らの罪を自覚させる。
それこそが、精神的な拷問なのだ。
『存在と無』で言われたように、「他者は、私と私自身の間の必要不可欠な仲介者」なのだ。従って、責め苦だけではなく、自分に対する信頼や自信の回復も他者を通して行われざるをえない。
だからこそ、ガルサンはエステルに対して「信頼」を求め、イネスには、自分が卑怯者ではないと説得しようとする。
ガルサンとエステルの会話に耳を傾けてみよう。

ガルサン
お前は俺を信頼するだろうか?
エステル
変な質問ね。私はいつもあなたを見張っているだろうし、あなたが私を裏切るとしても、それはイネスとじゃないわ。
ガルサン
それははっきりしている。(少し間を置き、エステルの肩を抱く手を放す。)俺が言った信頼って、それとは別のものだ。(彼は耳を傾ける。)ほら! ほら! 何を言いたいんだ。俺は自己弁護するためにここにいるんじゃない。(エステルに向かって) エステル、俺を信頼してくれなくちゃいけない。
(ジャン・ポール・サルトル『出口なし』)
エステルは信頼を肉体的な次元で捉え、夫婦や恋人の間で不義を働くといった意味で「裏切る」という言葉を口にする。それに対して、ガルサンは別の意味での信頼を問題にしているのだと言う。つまり、それは精神的な次元での信頼。
エステルから信頼されることで、ガルサンは自分に対する信頼を取り戻すことができると思っているからこそ、上の会話が交わされたのだった。

イネスが相手の時、ガルサンはより複雑な自分を見出す。
怒りにまかせて密室のドアをたたくと、突然ドアが開く。しかし、卑怯者ではないとイネスに認めさせない限り救われることがないのだと言い、地獄の部屋から出て行こうとしない。
ガルサン
お前のせいで、俺はここに残ったんだ。
イネス
私のせいですって? (しばらくの間を置く。)そう、じゃ、ドアを閉めて。ドアが開いてから10倍も暑いの。(ガルサンはドアの方に行き、ドアを閉める。) 私のせいですって?
ガルサン
そう。お前は、卑怯者が何か知ってるんだ。
イネス
知っているわよ。
(中略)
ガルサン
俺が説得しないといけないのはお前なんだ。お前は俺と同じ仲間さ。俺が出て行くって想像したかい? お前をここに残しておくことはできなかった。全てを考え、俺について何でもわかってるみたいにして、勝ち誇っているお前をな。
イネス
本当に私を説得したいの?
ガルサン
それ以外に俺にできることはない。俺には他の奴らの声は聞こえない。わかってるだろ。奴らは俺にとっては、もういないんだ。終わりだ。事は片付いている。俺はもう地上にはいない。卑怯者でさえない。イネス、ここにいるのはもう俺たちだけなんだ。お前とエステルの二人だけが、俺のことを考えている。でも、エステルはもうどうでもいい。だけど、お前は俺を憎んでいる。もしお前が俺の言うことを信じるなら、お前が俺を救うんだ。
(ジャン・ポール・サルトル『出口なし』)
ガルサンが自分を卑怯者ではなかったと信じるためには、イネスがそう思うことが必要なのだ。つまり、ガルサンの自己認識は、イネスという他者の視線によって左右される。

「意識とは常に何かの意識である」というサルトルの思想において、「私」と「何か」の関係は「必然的」なものではなく、「私」が視線を投げかける度に成立する「偶発的」なものだと考えられる。どのように意識化するのかは、「私」の「自由」に委ねられる。
その自由な選択に基づく行為の実践を真正面から引き受けるのか、なかったことにしたいと後悔するのか。その葛藤が、『蠅』のテーマだった。
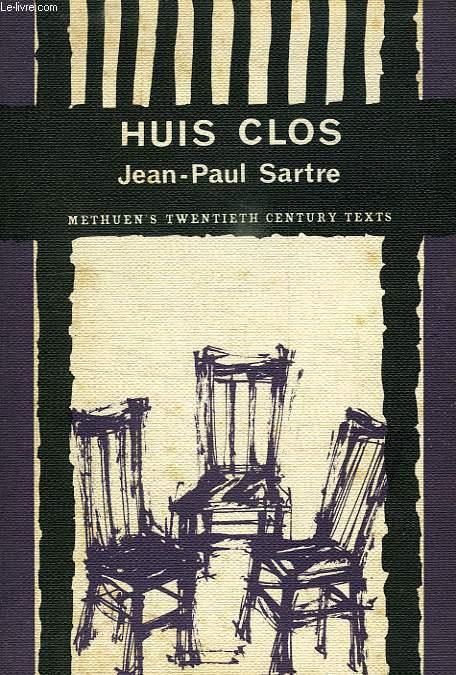
それに対して、『出口なし』では、意識の主体と客体の関係が逆転する。そこで問題になるのは、物や行為ではなく、「他者」。
「私」が意識の主体である時には、「他者」は物や行為と同じ次元の意識の対象にすぎない。
しかし、「他者」は物や行為とは違い、「私」と同様の意識を持つ。「他者」が主体となり、「私」に意識を向け、「私」を対象化する。その主客が逆転した状況において、「私」は、自分を自分で見るのではなく、「他者」の視線を通して自分を見る。
その時、「私」は自由な選択による行為を実践する存在ではなく、「他者」の審判を受ける存在になる。
「意識とは常に何かの意識である」という前提の中で、意識の対象となる何かが「他者」であるとき、その「他者」の視線が「私」に向けられ、「私」の自由を束縛し、「私」を苦しめる。それが、『出口なし』における拷問なのだ。
エステルの信頼やイネスの納得を自己確認のために必要とするガルサンには、そのことがはっきりとわかっている。
ガルサン
(前略)だから、本当にそれが地獄なんだ。前はそんなこと信じなかったかもしれないんだが・・・。思い出すだろ。硫黄、火刑のための薪の山、拷問の道具・・・。ああ! お笑い草だ。拷問の道具なんか必要ない。地獄とは、”他者たち”のことなんだ。
(ジャン・ポール・サルトル『出口なし』)
「地獄とは他人のことだ」というサルトルの有名な言葉は、このガルサンのセリフ(l’enfer, c’est les Autres.)から来ている。

この言葉は、しばしば、私たちの人間関係は多くの場合毒を含んでいるといった解釈される。しかし、そうした解釈は誤解だと、サルトルはあるインタヴューの中で述べている。
彼が意図したことは、私たちが自分自身を知るために「他者」は不可欠であり、私たちが自分を判断する時には、他者の視線を意識するか、あるいは他者の視線が混じり込む。
例えば、自分が恥ずかしい行動をしたと思う時、実際にその場に誰かがいようといまいと、他の人の目を意識してしまい、そのために恥ずかしさを感じる。自己意識を自分だけで構成することはなく、必ず他者の視線が存在する。
「私」の意識の中に「他者」の視線が入り込む。その状況をサルトルは「地獄」として提示したのだった。
ただし、私たちの実際の生活の中で、常に他者が私たちを拷問にかけるわけではない。信頼や安心を与えてくれる存在でもある。そのことは、ガルサンがエステルやイネスに求めるものがあることからも、否定できない。
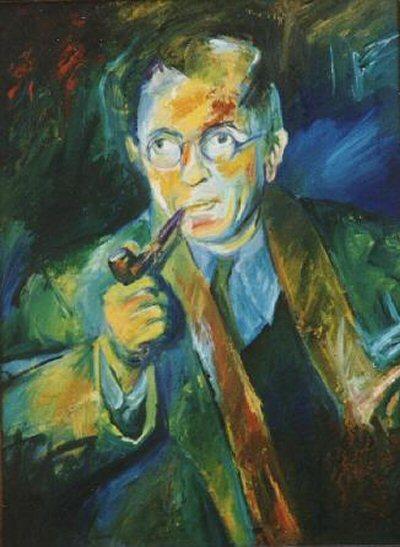
では、なぜサルトルが、他者の存在を地獄としたのだろう?
その理由は、彼の最も重要な主張が「自由」あでり、「人間は自由という刑に処せられている」という思想であるからだと考えられる。
「自由」を実践する際、人間は行為を行う「主体」である。何かを意識する際、対象との関係をその都度決めるのも、主体となる「私」。意識を向ける側であることが、「自由」の絶対的な条件になる。
それに対して、「他者」は、こちら側にいる「私」の意識の対象でありながら、あちら側から「私」に意識を向ける「主体」にもなりうる。その場合、「私」は「対象」になる。そして、「自由」はあちら側にある。
サルトルにとって、「自由」を奪われたこの状況が、「地獄」なのだ。
「地獄とは、”他者たち”のことなんだ。」というガルサンの言葉は、こうしたサルトルの思想に基づいて発せられたものであり、『出口なし』は、「私」と「他者」の相互性による葛藤を描き出している。

ジャン・ポール・サルトルの文学作品は、決して哲学的な内容を具体化しただけのものではない。文学はあくまでも文学であり、特殊な哲学専門の言葉を使わないで書かれた哲学書ではない。
その一方で、『嘔吐』や『蠅』『出口なし』を、ある程度サルトルの意図に即して理解するためには、『存在と無』などで展開された彼の思想を知ることが前提となる。
『嘔吐』とロカンタンは、公園のベンチの下の木の根を見ることで、「吐き気」がどこから来るのか知る。そして、私たち読者は、そこで実存を彼とともに体感する。それは文学的な体験だ。
ただし、「実存は本質に先立つ」という哲学の思想を知られなければ、ロカンタンの「吐き気」の意味が理解できない。その思想を知ることで実存の意味を理解でき、さらに、哲学の主張を体感することもできる。
『蠅』においては、オレステスとエレクトラの対照が、自由に選択された行為を実践する意義を浮かび上がらせる。
『出口なし』では、自己と他者の相互性が劇全体を支配し、人間は密室における裁判所の中で、検事であると同時に被告でもあるという状態に置かれている状況が描き出される。
二つの劇の対比は、哲学の用語を使えば、「対自」と「対他」に焦点を当てることになり、サルトル哲学の二つの側面を観客に伝えることになる。
このように、ジャン・ポール・サルトルの文学と哲学は、どちらもそれだけで自立しながら、お互いにお互いを補足する存在となっている。
参考文献
ジャン・ポール・サルトル『嘔吐』鈴木道彦訳、人文書院。
『サルトル全集』第8巻、蠅、出口なし(伊吹武彦訳) 、恭々しき娼婦(芥川比呂志訳) 、人文書院。
ジャン・ポール・サルトル『存在と無』全3巻、松浪信三郎訳、ちくま学芸文庫。
。。。。。。
アニー・コーエン・ソラル『サルトル』石崎 晴己訳、白水社、文庫クセジュ。
海老坂武 『サルトル: 「人間」の思想の可能性』 岩波新書 。
澤田直『サルトルのプリズム: 二十世紀フランス文学・思想論』法政大学出版局。