(2)不条理な生

アルベール・カミュの作品にはしばしば「不条理」というレッテルが貼られる。そこで、不条理とは何かを調べてみるのだが、説明が抽象的で、ピンとこないことが多い。
ある辞書の定義では、「事柄の道筋が立たないこと」と簡潔に記され、「人生の不条理」という例が挙げられている。
哲学の用語としては、「世界に意味を見いだそうとする人間の努力は最終的に失敗せざるをえない。そのような意味は少なくとも人間にとっては存在しないからである。この意味での不条理は、論理的に不可能というよりも人間にとって不可能」といった言葉で説明される。
カミュが不条理について哲学的に考察した『シーシュポスの神話』でも、「この世界自体は合理的なものではない。不条理というのは、不合理なことと明晰さを求める激しい欲望との対立である。その欲望の訴えかける声が、人間の最も深い部分で鳴り響いている。不合理であることと明晰を求める欲望の間のズレが大きくなるほど、不条理は大きくなる。」といった説明がなされている。
これらの説明では「不条理」という言葉が何を意味しているのかはっきりしないし、私たちにとってどのような意味があるのかもわからない。

そこで、もう少し具体的に考えてみよう。
例えば、理性や人間性の不合理を追求したカミュの代表作とされる『異邦人』において、主人公ムルソーは、母の死に無関心なように見え、明確な動機もなく殺人を犯し、裁判で死刑を宣告されながら幸福であると感じる。
では、ムルソーの行為や感情が「馬鹿げたこと」=「不条理」なのだろうか? もしそうではないとすると、何が「不条理」なのだろう?
A. 「不条理」はどこにあるのか? — 『異邦人』
i. 対立するもの
『異邦人』は二つの部分で構成される。
第1部:ムルソーの行動 — 母親の葬儀への参列、恋人マリーとのやり取り、海岸でのアラブ人殺害 —が、時間的な経過に従って語られる。
第2部:逮捕されたムルソーが裁判にかけられ、彼の行動に対する断罪と弁護がなされる。
この二部構成が、「不条理」がどこにあるかを示す重要な鍵となる。

第1部では、以下のような出来事がムルソーの回想風な文章で語られる。
アルジェリアのアルジェに暮らすムルソーは、母親の死を知らせる電報を受け取り、葬儀のために養老院に向かう。しかし、普通の人のように母の死を悼み、涙を流すといったそぶりを見せず、感情を表すことをしない。
翌日、アルジェに戻ると、海水浴場でマリーと会い、コメディ映画を見たり、夜を共にする。
その後、隣人のレイモンという男の相談に乗り、アラビア人たちとの揉め事に足を突っ込むことになる。
週末、ムルソーはマリーと一緒にレイモンの友人の海沿いの別荘に招待される。そこでマリーに結婚したいかと尋ねられ、そんなことは重要ではないといった曖昧な返事をする。

日曜日の午後、レイモンたちと海岸線を散歩中に、いざこざの最中のアラブ人二人と偶然出会い、喧嘩になる。ナイフで斬りつけられ怪我をしたレイモンが拳銃を持っていることを知ったムルソーは、問題が起こるといけないからと言い、拳銃を預かる。
その後、一人で海岸を歩いている時、一人のアラブ人と鉢合わせ、相手がナイフを抜いたため、拳銃で彼を打ってしまう。最初は1発、続けて4発。

第2部は、第1部で語られた出来事を前提にし、裁判が繰り広げられる。
その中で、殺人に対する量刑を軽減するために論理を組み立てようとする弁護士に対し、ムルソーが無関心だったり反発したりする心の内が明かされる。
死刑判決が出た後、独房を訪れた司祭に対して懺悔することを拒否し、「あなたのために祈る」という最後の言葉を聞くと、それまではほとんど大きな反応を示さなかったムルソーの感情が爆発する。
最後に、ムルソーは、心の中に平和な気持ちが戻り、自分が幸福であると感じ、死刑執行の日には、群衆が彼を憎しみの叫びで迎えることを望む。
こうして物語を大まかにたどると、対立するものが何かが見えてくる。
一方には、ムルソー以外の人々が自然に当たり前だと思う人間的な反応だったり、行動の動機などがある。
他方には、社会通念とかけ離れたムルソーという存在が浮かび上がる。
「不条理」が矛盾する二つの要素の対立によって成立するとしたら、ムルソーの行動や感情の動きだけが不合理で説明不能というだけではなく、対立するもう一つの側、つまり誰もが当たり前と思っている社会通念があり、そのせめぎ合いの中に「不条理」が発生する、ということになる。
そのことについて、母の死に対する反応と、殺人の動機という二つの点から具体的に考えてみよう。
ii. 社会通念に従わない変人
『異邦人』は母に関する次の言葉で始まる。
今日、母さんが死んだ。たぶん昨日かもしれない。でもよくわからない。施設から電報を受け取った。「母死去。明日埋葬。敬具。」こんなのに何の意味もない。たぶん昨日のことだった。
普通であれば、自分の母親が死んだら大変なショックを受けるし、死んだ日が昨日なのか今日なのか迷うことなどない。この冒頭の一節は、そうした「当たり前」に逆行するムルソーを登場させることで、読者に衝撃を与える効果を生み出している。

そのことはカミュ自身が最もよくわかっていたに違いない。
彼は、1957年にノーベル文学賞を受賞した際、学生たちとの討論会で、アルジェリア独立戦争における過激派たちに対する意見を問われた際、「私は正義を信じています。しかし、正義よりも前に母を守るでしょう」と述べたことがある。
彼にとっても、他の人々と同じように、母親はそれほど大切な存在なのだ。

母親を指す言葉として使われる「母さん」という言葉は、すぐ次に出てくる「母」という客観的な言葉とは異なり、ムルソーが母親に対して抱く気持ちを強く表現している。その愛情を前提にした上で、彼は施設からの電報に無感動で無関心な様子を示す。
つまり、「普通であればこうするだろう、こうすべきである」といったことと、彼の反応の間には大きなズレがある。だからこそ、ムルソーは「異邦人」なのだ。
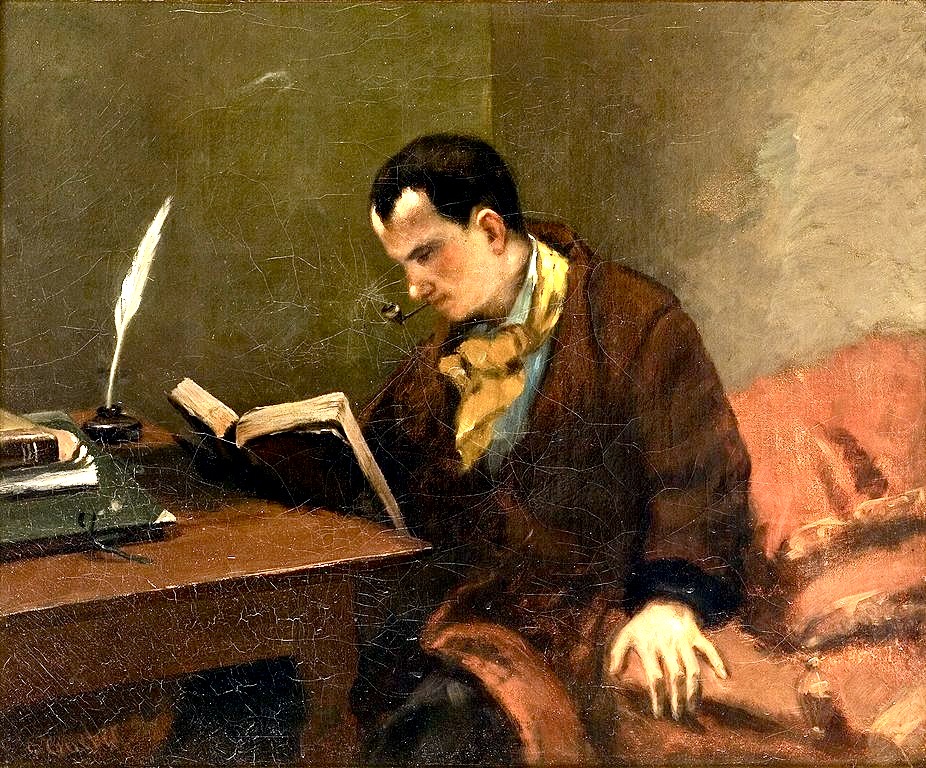
その「異邦人」という言葉は、19世紀フランスを代表する詩人シャルル・ボードレールの散文詩「異邦人」を思わせる。
その中で、謎の男は、「父母も兄弟姉妹もいない。友だちという言葉の意味など知らない。祖国がどの緯度にあるのかも知らない。美女も愛さないし、黄金も神も憎んでいる。」と告白する。
このように、一般的には誰もが大切だと思うものは否定される。
そして、「何を愛するのか?」という問いかけに、「雲・・・。流れていく雲・・・、あちらに、・・・あちらに・・・。素晴らしい雲だ!」と答える。
こんな詩的な言葉をムルソーが綴るとは思えないが、しかし、彼が社会通念に対して取る姿勢は、ボードレールの謎の男と同じタイプに属する。
その結果、一般論を何気なく受け入れ、それに従って行動する人々にとって、ムルソーの一連の行動は謎でもあり、受け入れられないものになる。

では、彼はたんに変な奴なのだろうか?
それとも、私たち自身も、みんながなんとなく自然だと思うことに無理に合わせる必要はなく、逆に、それに従うことを強要する雰囲気こそが一人一人の心を抑圧しているのではないのか?
こうした問いは、21世紀の日本でも、多くの人々が自分に問いかける問題に他ならない。
一方では、自分の思うままでいいという言葉に耳を傾け、自由を欲する。しかし他方では、みんなと違うことで排除され、不利益を蒙るのではないかと恐れる。
「不条理」がそうした板挟みの状態から生じると考えると、カミュがテーマとした問題が、現代の私たちと直接関係することに納得がいくだろう。
iii. 殺人の動機を巡る議論
『異邦人』第2部の中心を占めるのは裁判を巡る問題。
裁判において、検察側は、被告人が犯した犯罪の証拠を示し、被害の大きさや犯罪の手口などを考慮した上で、どの程度の重さの罰がふさわしいかという意見を述べる。
それに対して、弁護側は、被告人の立場に立ち、実際に犯罪行為を犯した場合でも、そこに至るまでには様々な事情があったことなどを提示し、刑罰を軽減するように求める。
そのどちらの側に立つとしても、動機や被告人の人物像を明らかにすることで、判決を下す裁判官や陪審員たちに自説の正当性を訴えることになる。
従って、裁判においてやり取りされる言葉は、”本当らしさ”をアピールする必要があり、そのためには誰もが納得するもの、つまり”通説に従ったもの”であることが求められる。
そのように考えると、第2部の役割が明らかになる。
裁判で交わされる言葉は、ムルソーの行動を社会通念を通して解釈する試みであり、ムルソーの無関心な様子はそうした解釈とのズレを際立たせる。

実際に、裁判では、アラブ人を殺した動機と同時に、母の葬儀に際してのムルソーの態度が取り上げられ、検察官や弁護士は、全てをある一定の論理に従って整理しようとする。
それに対して、様々な質問に「なぜかわからない」と答えるムルソーは、殺人の動機を問われると、「太陽が眩しかったから」と言う。
その答えに説得力はなく、何か理由を隠しているのか、変な奴だとしか思われない。実際、母の埋葬の時も、感情を表さない非人間的な変わり者だと見なされた。
こうした判断の背後には、肉親の葬儀の際の振る舞いにはコードがあり、殺人にはそれなりの理由があるという、暗黙の了解がある。
社会通念とムルソーの間のズレを最も端的に示すのは、弁護士が殺人に関して「私」という主語で語る場面。
午後、大きな扇風機が、法廷の重々しい空気を絶えずかき混ぜ、陪審員たちの持つ様々な彩りの小さな団扇は、みんな揃って同じ方向に動いていた。ぼくの弁護士の口頭弁論は、いつまでも終わらないのではないかと思われた。たまたま、ある時、彼の言葉に耳を傾けると、彼は、「本当に、私が殺したのです。」と言っていた。その後も、同じ調子で、ぼくのことを話す度に、「私」と言った。ぼくはとても驚いた。それで、警官の上に体を乗り出し、なぜと尋ねた。警官はぼくに静かにするように言ったが、その後で、こう付け加えた。「どの弁護士もそうするんだ。」その時に考えたことは、それがぼくをこの件からさらに遠ざけ、ぼくをゼロの状態にし、ある意味では、ぼくの代理になるということだった。でも、今思うと、もうそれ以前に、ぼくは法廷から遠くにいたと思う。

この時、弁護士は検察官や陪審員たちと同様に社会通念の体現者であり、その人間がムルソーの行動を社会通念の言葉に従い弁護しようとする。
そんな法廷の中にムルソーの身体はあるのだが、心はそこにはない。
弁護士が「私が殺した」ということに驚くムルソーと、「どの弁護士もそうするんだ」という警官の言葉の対比は、ムルソーが法廷の中で完全なる異邦人であることを浮き彫りにする。
『異邦人』は次の言葉で締めくくられる。
全てが成し遂げられ、ぼくがそれほど孤独ではないと感じるために、ぼくに残されているのは、処刑の日、多くの観客がいて、ぼくを憎しみの叫びで迎えてくれることを望むことだけだった。

多くの観客とは、社会通念に当たり前に従う人々。孤独は自由の代償であり、人々の憎しみの叫びは、ムルソーが社会通念から自由であることを確認させてくれる叫びだといえる。
処刑される際に、憎しみの叫びに迎えられることで、彼は異邦人としての自己確認をすることになる。だからこそ、それを望むのも自然なことだ。
このように考えてくると、「不条理」がどこにあるのかが見えてくる。
それはムルソーの側にあるのでも、「こうあるべき、こうすべき」という側にあるのでもなく、その二つが対立する中にある。
そして、それぞれの個人には、「こうあるべき、こうすべき」に従わない「自由」がある。その一方で、その選択は多くの人々との対立を招き、孤独に陥らせる。自由だが孤独でもある。
それがムルソーの選択だった。
B. 「不条理」と「自由」 — 「カリギュラ」

「不条理」であることを受け入れるのであれば、個人は100%「自由」であることができるのか?
この問題は、アルベール・カミュが『異邦人』を執筆する以前、「カリギュラ」の中で取り組んだものだった。
「カリギュラ」が上演されたのは1945年だが、執筆されたのはカミュがまだアルジェリアにいた1938年のことであり、1942年に刊行された『異邦人』よりも前だった。
ローマ帝国皇帝のカリギュラは、妹であり愛人でもあるユリアの死を境にして、善政を施す君主から暴君へと豹変する。そして、月を手に入れることを望み、人々から財産を奪い、部下を殺し、妻を奪い、グロテスクな化粧をして神を冒瀆するような乱痴気騒ぎをするようになる。
情婦セゾニアを始め少数の人間はカリギュラを憎めないのだが、多くの家臣たちは皇帝から離反し、暗殺計画を進める。
その計画が発覚した時、カリギュラは首謀者であるケレアを罰しない。そして、最後は暗殺者たちの手にかかり、命を落とす。

こうした展開を持つ戯曲が焦点を当てるのは、カリギュラの変身とその結果。
善政を施すことは、社会一般の要請に応える政策を行うこと。それに対して、暴君は、人々の望みとは逆の行動を取り、残虐な行為を厭わない。
月を手に入れるという欲望は、カリギュラが一般常識から完全にかけ離れてしまったことを象徴する。そして、家臣たちに対して横暴のかぎりをつくす行為は、彼が自由を100%行使する姿でもある。
こうしたカリギュラはムルソーと全く違うように見えるが、社会通念から完全に自由であるという点では共通している。
違いは、ムルソーは普通の市民であり、カリギュラは皇帝であること。
ムルソーは、他者に影響を及ぼす立場になく、他者に対する働きかけを行わない。
他方で、カリギュラは家臣たちに囲まれ、彼らを抑圧する。カリギュラの自由は他者の自由と鋭く対立し、他者の自由を認めない。

そうした視点から見ると、カミュが「カリギュラ」でテーマにしたのは、二つの自由の対立だったことがわかってくる。
自由を100%行使することが他者の自由の抑圧に繋がるとしたら、個人の自由はどこまで認められるのか?
人は他者たちに対して自由であることはできない。としたら、どのようにして自由であることができるのか?
その問いに対して出したカミュの結論は、自由を完全に行使する場合、他者の自由の行使も認めなければならない、というものだった。
暴君カリギュラの暗殺は、他者の自由の行使に他ならない。
カリギュラは暗殺計画を発見してもケレアを処罰しない。それは自らの暗殺を認め、促すことでもある。カミュ自身の表現によれば、高次な自殺、つまり他者による自殺だ。
愛と中庸の作家アルベール・カミュにとって、カリギュラ的な自由は認められない。”私の自由”と”他者の自由”はお互いに調整が必要となり、それができるとき連帯が生まれる。
こうした思考の具体的な表現は、「反抗」のテーマ群の作品の中で繰り広げられることになる。
C. 「不条理」の重荷から幸福へ — 『シーシュポスの神話』

カミュは「不条理」を具現化する人物として、古代ギリシア神話の登場人物シーシュポスを選んだ。
シーシュポスは、神々を欺いたために、思い刑罰を受けなければならない。その刑罰とは、冥界の最奥にあるタルタロスで、巨大な岩を山の頂上まで持ち挙げるというものだった。ただし、目的に到達しそうになると、岩はその重みで底まで転がり落ちてしまい、山を下り、再び同じ岩を頂上まで持ち挙げるなければならない。しかも、その無益な行為を永遠に繰り返さなければならない。
i. 上り — 重荷
落ちることが決まっている巨大な岩を持ち上げる。その行為はまさに「事柄の道筋が立たたないこと」、「明晰さと対立する不合理なこと」であり、シーシュポスの課せられた刑罰は「不条理」を象徴するのに相応しい。
カミュは『シーシュポスの神話』の中で、ギリシア神話の英雄を次のように定義した。
すでに理解されたことと思うが、シーシュポスは不条理なヒーローなのだ。様々な情熱によっても、苦しみによっても、そうなのだ。神々を軽視すること、死を憎むこと、生きることに対する情熱、それらが、言葉にできないほどの苦しみを彼にもたらした。全存在をかけて努めても、何一つ達成できないという苦しみだ。それが、この地上に対して抱く数々の情熱のために、支払わなければならない代価なのだ。

岩は必ず落ちると定められている。従って、全力で持ち挙げたとしても目的は達せられず、無意味に終わる。それを永遠に繰り返すことを強いられるとしたら、気の遠くなるような苦痛と苦悩を感じるだろう。
ところで、私たちは、シーシュポスの刑罰を知った時、彼が巨岩を山の上に持ち挙げようと力を込めている姿を思い描かないだろうか。
実際、絵画で描かれるシーシュポスは、力を込めて岩を押し上げる姿で描かれている。
また、カミュの不条理に関する数々の考察でも、岩を持ち上げることの苦悩と空しさに視線が向けられる。
そこで焦点が当たるのは、岩を持ち上げる苦役だ。
ii. 下り — 幸福
ところが、アルベール・カミュがとりわけ注目するのは、上りではなく、下りであり、岩を持たない時のシーシュポスなのだ。
夢中で何かをしているとき、どんなに肉体的に大変だろうとも、なんとかその動きを続けることができる。先のことは考えず、今に集中し、力を込める。
しかし、一端その動きが止まり、ふと身体の力が抜ける時、再び辛い労働をしなければならないと考える。その時にこそ、精神的な辛さがどっと押し寄せてくる。
カミュの視線が山を下るシーシュポスに向けられるのは、肉体ではなく、精神あるいは意識に注目するからに他ならない。
この帰り道、この休息の間こそ、シーシュポスが私の興味を引くのだ。数々の石のすぐ近くで苦しむ顔は、すでにそれ自体が石になっている! 私には、この男が下っていく姿が目に見える。重々しいが均一な足取りで、いつ終わるとも知れぬ苦しみに向かっていく。ひと息つくようなこの時間、不幸と同じように確実に戻ってくるこの時間、この時間は意識の時間なのだ。頂上を離れ、神々の住む洞窟へと少しづつ沈んでいく瞬間、その瞬間毎に、彼は運命よりも上にいる。岩よりも強いのだ。

この一節において、カミュが神話の読み替えを行っていることに注目しよう。
シーシュポスに対する神々の刑罰は、山の上に岩を持ち上げる空しい行為を永遠に反復すること。そこで描き出されるのは、落ちることが定まっている巨石を持ち上げる姿。下りの姿はあまり意識されない。
カミュはそうした紋切り型を超えて、徒労と予め分かっている行為に向かうシーシュポスの姿を浮かび上がらせる。
その理由はどこにあるのだろう?
下りの道のり、精神的な苦悩は、肉体を駆使している上りの時よりもはるかに大きい。それにもかかわらず、「不条理なヒーロー」は山を下る。その行程が悲劇的なことは疑いを入れない。
しかし、カミュはそこに悲劇的な運命とは異なる要素を導入する。それはシーシュポスの「意識」。
シーシュポスは「いつ終わるとも知れぬ苦しみに向かっていく」のだとカミュは言う。
つまり、上りと同様に下りも神々によって定められた運命とするのではなく、シーシュポスの意志によるものだとする。
彼は自らの行いが「不条理」だと意識しながら、山の麓へと向かっていく。だからこそ、山を下る時間が「意識の時間」と呼ばれる。
そして、「その瞬間毎に、彼は運命よりも上にいる。岩よりも強い。」
『シーシュポスの神話』の最後、山の麓で次の苦役に備える不条理なヒーローの姿が浮かび上がる。
シーシュポスを山の麓に残しておこう! 彼の重荷はいつでも再び見出される。とにかく、シーシュポスはより高度な忠実さを教えてくれる。神を否定し、岩を持ち上げる忠実さだ。彼はまた、全てが善だと判断する。今後は主人不在のこの世界が、彼には不毛だとも無価値だとも思えない。この石のそれぞれの粒、夜に包まれたこの山のそれぞれの鉱物の輝き、それだけで一つの世界を形作るのだ。頂上へと向かう戦いだけで、人間の心を満たすためには十分なものだ。シーシュポスは幸福だと想像しなければならない。

「神を否定し、岩を持ち上げる」とは、その行為が神による強制ではなく、自らの意志による自発的な行為であることを意味する。
山の麓のシーシュポスは、持ち上げた巨石は常に落下するという不条理を意識した上で、再び山頂を目指すことを自らの意志で決定する。
その行為を実践する過程で、山の中に潜む鉱物が夜の闇の中で美しい輝きを放ち、そこに一つの世界が形作られる。岩を頂点まで持ち上げることが目的ではなくなり、その瞬間その瞬間が貴重なものとなる。
その世界を形成する不条理のヒーロー、シーシュポスは幸福だ。カミュはそう断言する。
「上り」から「下り」への視点の変更は、「不条理」の意識化が一人一人の人間にどのような変化をもたらすかを示す指針なのだ。
。。。。。
シーシュポスに対する神あるいは主人を、「こうあるべき」といった社会通念や死刑執行の際に喜びの声を上げる人々と置き換えれば、シーシュポスはムルソーと重なることになる。
彼らは不条理を意識し、その状況を自由な選択として受け入れることで、幸福であることができるのだ。
ただし、その自由は「個人としての自由」であり、「カリギュラ」で見たように、他者の自由と対立する。
その思考を押し進めながら、アルベール・カミュは、「不条理」から「反抗」へとテーマを移行し、個人の問題から他者との関係へと思考を進めていく。