(3)「反抗」と「中庸」
「不条理」はあくまでも個人の問題だったが、「反抗」では集団内での連帯へと問題が移行する。

『ペスト』は、パンデミックに襲われた町の中で、医師のリユーを中心に、様々な人々がペストと戦う。その姿は、社会から孤立した異邦人ムルソーとは違っている。
『正義の人々』は、帝政ロシアにおけるテロリズムをテーマとした戯曲だが、暗殺を実行するカリャーエフを含むテロリスト・グループに焦点が当てられている。
『カリギュラ』の主役は暗殺されるローマ皇帝カリギュラであり、暗殺する家臣たちの連帯に光が当てられてはいない。
その対比は、「不条理」が個人の問題あり、「反抗」が連帯を問題にしていることを、はっきりと示している。
『反抗的人間』の中で、カミュは、デカルトの「我思う、故に我在り」をもじり、こんな表現を使う。
我反抗す、故に我ら在り
反抗するのは「我」、つまり個人なのだが、反抗することで存在するのは「我ら」、つまり複数の人間になる。
では、「反抗」がなぜ連帯につながるのか? そして、「反抗」とは何に対する反抗なのか?
A. 「愛」と「連帯」 — 『正義の人々』

『正義の人々』は、20 世紀前半の帝政ロシアで実際にテロリストとして活動したボリス・サヴィンコフが1926年に出版した回想録『テロリストの回想』に基づき、カリャーエフが1905年にセルゲイ大公を暗殺した事件を題材にしている。
大公の馬車に爆弾を投げつけるカリャーエフは単独犯ではなく、恋人のドーラ、リーダーのアネンコフ、先鋭的な考えを主張するステパン、穏健なヴォワノフとグループを作り、絶えず議論を絶やさない。

そこでのアルベール・カミュの興味の中心が彼らの「連帯」にあることは、暗殺されるセルゲイ大公に対する無関心と正比例の関係にある。
そのことは、『カリギュラ』の中で、皇帝を暗殺する家臣たちにほとんど注意が払われないことと照らし合わせてみると、さらにはっきりとする。
カリャーエフたちは二度暗殺を試みる。
i. 最初の暗殺 — 子どもの存在
最初は、セルゲイ大公がオペラに向かう馬車。爆弾を投げようとする瞬間に、馬車の中に二人の子どもがいるのがカリャーエフの目に入る。そして、爆弾を投げるのを止める。
では、恐怖政治を終わらせるためであれば、子どもの命を犠牲にしてもいいのか?
それが、暗殺を中止した後で、テロリストたちが議論するテーマになる。

ステパンは、正義という”大義”のためであれば、子どもの命を犠牲にすることはしかたがないと主張する。
他の仲間たちは、無実の人の血を流させることは一般の理解を得られないと考え、カリャーエフが爆弾を投げなかったことに賛同する。
この意見には、アルジェリア独立戦争の際に過激な行動に走る活動家について問われ、「私は正義を信じています。しかし、正義よりも前に母を守るでしょう。」と応えたアルベール・カミュの「愛」が反映しているに違いない。
では、大公を暗殺することは許されるのか? 大公も人間ではないのか? そうした疑問が、二度目の試みでテロに成功し、大公の命を奪った後の展開の中心となる。
ii. 2度目の暗殺 — 大公の命と”大義”の比重

カリャーエフは逮捕、投獄され、死刑判決を受ける。その牢獄で、権力の側は他のテロリストたちを捉えるため、カリャーエフが仲間を裏切れば、死刑を免れることができるという罠を巡らせる。
また、カリャーエフが裏切ったという噂を流し、仲間たちを動揺させる。
カリャーエフ:(前略) おれは戦争捕虜だ。被告人じゃない。
スクラートフ:そう思いたいならそうすればいい。だが、確かに被害はあった。大公と政治は考えないでおこう。しかし少なくとも、人間が死んだ。それもなんという死にざまだったことか。
カリャーエフ:おれが爆弾を投げたのは専制政治に対してだ。人間に向かってじゃない。
スクラートフ:確かにそうかもしれない。しかし、爆弾を受けたのは人間だった。そのことで彼の都合のいいようにはならなかった。わかるかい。身体を見たら、頭がなかった! それ以外の部分に関しても、それとわかったのは、腕一本と足の一部だけだった。
カリャーエフ:おれは評決を実行したんだ。
権力を体現する警察庁長官のスクラートフは、大公も人間であることを強調し、テロは殺人だとカリャーエフを問い詰める。
カリャーエフの”大義”は人々を苦しめる専制主義的な恐怖政治を消滅させることにあった。
その視点からは、大公を人間とは見なさない。
馬車の中にいたのは恐怖政治を象徴する大公だけであり、殺害したのは恐怖政治であって、殺人を犯したのではない。
それに対して、スクラートフは、大公が一人の人間であることをはっきりと意識させるために、爆弾を投げつけられてバラバラになった死体の様子まで語る。
その対立する二つの立場は、”大義”と”個人の命”の対比を浮かび上がらせるものであり、正義よりも母を守るカミュの思想からすれば、カリャーエフはスクラートフの論理に屈するしかなくなる。

さらに、その後の展開では、警察庁長官の後に大公夫人も監獄に足を運び、夫を殺害された妻の悲しみを語り、カリャーエフの「愛」の心に訴えかけようとする。
その論理に従えば、暗殺は正義のためだったという主張を変えないカリャーエフは、自己矛盾しているのではないか?
そうした状況をカミュがあえて設定したのは、『正義の人々』の中心的なテーマが「連帯」であるからだ。
そのことは、カリャーエフが「おれは”評決”を実行したんだ」という言葉にも込められている。つまり、暗殺は個人的な選択ではなく、裁判でと同じように、グループで決定したものなのだ。

これらの考えは、暗殺の成功を知った時のドーラの言葉とも対応している。
ドーラ:大公を殺害したのは私たちよ! 大公を殺害したのは私たちよ! それは私なの。
「私たち」と「私」の混同は、カリャーエフの行為がグループ全体の決定によることを暗示し、連帯感を強く感じさせる。
権力の側の警視庁長官や大公夫人が大公も人間であり、暗殺は殺人だと言う時、その本当の狙いはカリャーエフの「愛」を利用して、テロリスト・グループを裏切らせることにあった。
カリャーエフはその罠に陥ることなく、恩赦で救われる誘惑に屈することもなく、「私」が「私たち」である「連帯」を守りきる。
それは、「我反抗す、故に我ら在り」の思想と対応する状況だといえる。
B. 「反抗」 — 『ペスト』
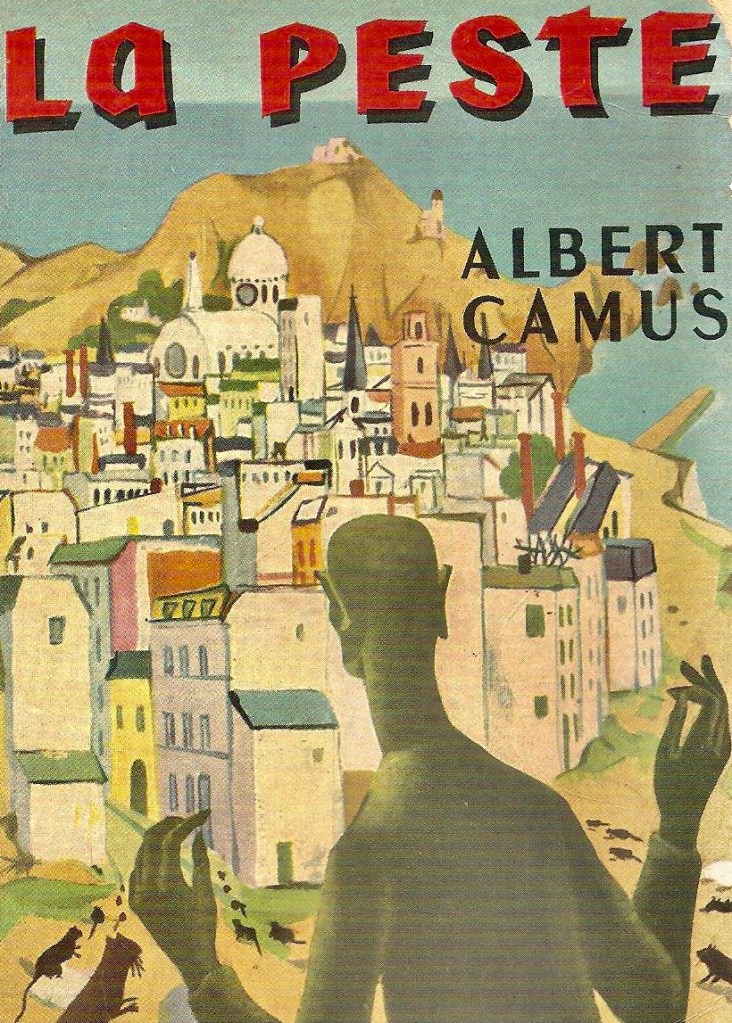
『正義の人々』であれば、テロリスト・グループが闘うべき相手は恐怖政治の頂点に立つセルゲイ大公であることがはっきりしている。
しかし、ペストと戦うと言う時、状況はまったく異なる。
ペストには実体がなく、ペストそのものを倒すわけにはいかない。猛威を振るうパンデミックを前にしてできることといえば、予防に努め、患者に対して治療を施し、被害を最小限に抑えながら、伝染病の終息を待つしかない。
戦いはペストそのものを倒すことではなく、人々が連帯して、ペストがもたらす災禍に対処することになる。
i. 『異邦人』から『ペスト』へ
「連帯」を軸に考えると、『異邦人』から『ペスト』への移行がどのような意味を持つかがわかってくる。

『異邦人』のムルソーは、人々が普通だと感じ考える社会通念に従わない行動を取る。彼はそうしたものから「自由」なのだが、それだからこそ、社会通念に従う人々とぶつかり、その対立から「不条理」が生じる。
『ペスト』では、パンデミックに襲われた地域の全ての人々が、行動や思考を規定している社会通念をペストという具体的な病として意識化し、全ての人がその力を思い知る。
その時、住民全員がムルソーの立場に置かれるといってもいいだろう。言い換えれば、一人一人が、なぜ自分の住む町をペストが襲うのか? なぜこの時代にペストが発生するのか? といった疑問を抱き、「不条理」を感じる。
その際、ペストに対して個人で戦っても意味はなく、人々が「連帯」して対処しなければ、被害は拡大するばかりになってしまう。
そうした対応を、カミュは「反抗」と呼ぶ。
『異邦人』は「不条理」の個人的な気付きを描き、『ペスト』では人々が「不条理」な状況の中で連帯して対処する「反抗」がテーマとなる。
ii. 「自由」と「連帯」
新型コロナウイルスが蔓延した際に私たち自身が経験したように、個人としてできることは限られていて、社会全体で伝染病の蔓延を防ぐための対策に従うことが必要になる。
ただし、その際には、個人の自由は制限され、行政の指示に従うことが求められる。
反マスク派、反ワクチン派が一定数存在し、指示に従わない自由を主張したことは、自由の問題を考える上で、一つの指針となる。

「反抗」は複数の人間の「連帯」を前提にする。そのために、『ペスト』には数多くの人物が登場する。
中心となるのは、医師のベルナール・リウー。彼はペストに襲われたオランの町での出来事を、「年代記」風の比較的客観的な筆致で語っていく。
ジャン・タルーは、身元がはっきりせず、謎めいた人物。リウーと友情を結び、彼に協力するが、最後はペストで命を落とす。彼の残した手記がリウーの「年代記」に挿入される。
ジョセフ・グランは、市役所の職員で、作家になる夢を持ち、文章の推敲を重ねている。
レイモン・ランベールは、パリからやって来た新聞記者。初めのうちはあらゆる手段を使いオランから脱出しようと試みる。しかし、苦労の末脱出が可能になったとき、突然考えを変え、オランに留まり、リウーたちのグループに加わる。
リウー、タルー、グラン、ランベールたちは、保険隊を組織し、人々の看護に奔走する。彼らの行動は、一人の暴君を倒すテロリズムでもなく、専制的な体制を転覆させる革命でもなく、ペストという「不条理」な状況に対する「反抗」とみなされる。
パヌルー神父は、かたく神を信じ、人々にキリスト教の見地から、ペストに対する心構えを説教をする。
コタールは、過去に犯罪を犯したらしく、現在は仕事もなく、部屋の中で首を吊るといったこともする。そして、ペストが終息した直後、町で銃を乱射し、逮捕される。

彼ら以外にも数多くの人間が登場するのだが、とりわけ注目したいのは、たとえ保険隊というグループの中でも、一人一人の行動は異なり、自由を束縛されてはいないということ。
その典型は、パリから来た新聞記者ランベール。
リウーたちはランベールが脱出しようとするのを知ると、手助けする人間たちを紹介する。脱出する自由も、治療活動に参加しない自由も確保されていて、「連帯」を強要されることはない。
ただし、自由が他の人の自由とぶつかる場合には、100%の自由は認められないというのが、アルベール・カミュの基本的な思想だった。
そのことは、戯曲『カリギュラ』を1944年に刊本した際に、孤独なローマ帝王カリギュラについて次のように記していることからも推測することができる。
人は他の人々に対して自由であることはできない。では、どうやって自由であることができるのか?
この問いかけに対する答えは、『ペスト』の中で、理論ではなく、人々の具体的な行動によって描き出される。
コタールは、救援活動に参加せず、ある意味で「自由」に振る舞い、最後は警察に逮捕される。その意味で、100%の自由を行使することは許されない。
他方、ランベールは、オランから脱出する「自由」と同時にそこに留まる「自由」も持ち、結局はリウーたちの「連帯」に加わる。
ペストという不条理な災禍の中、どのようにしたら自由でありうるのかを示す最適な例が、ランベールだといえる。
iii. 「愛」の表現
「年代記」を書き綴る医師ベルナール・リウーたちの献身的な活動は、パンデミックからできるかぎり多くの人々を守ることに大きな貢献をする。
そこには、人間に対する「愛」の精神が強く感じられる。

それ以上にアルベール・カミュの「愛」が強く反映するのは、小さな子どもの死を描いた場面だ。
その子は主要な登場人物たちの一人ではない。父親のオトン判事も大きな役割を果たすわけではない。それにもかかわらず、無垢な子供の死が描かれた場面は「年代記」の客観的な記述とは異なり、読者の胸を強く打つ文体で描かれる。
その死は、血清の準備が整い、ペストの終焉が見え始めた直後のことで、希望があるだけにますます悲劇性が高まる。
その子は胃を締め付けられたように再び体を二つに折り、弱々しいうめき声を上げ、長い間、身体を丸めたまま動かなかった。痙攣して小刻みに身体を揺らす様子は、弱々しい骸骨がペストの激しい風にさらされて折れ曲がり、熱の息吹に繰り返し襲われ、きしんでいるかのようだった。発作が収まると、子供は少し体を緩めた。熱が引き、彼を置き去りにしたように見えた。ゼーゼーと息をする姿は、湿り気と毒に満ちた岸辺に横たわっているようで、そこでは休息がすでに死に似ていた。三度目に熱の波が襲いかかり、少し体を持ち上げた時、子どもは体を丸め、焼き尽くすような炎を恐れてベッドの奥に体を引っ込め、狂ったように頭を振り、掛け布団を投げ飛ばした。大きな涙の粒が発熱した瞳の下から溢れ出し、鉛色の頬をつたい始めた。発作が終わると、疲れ果て、骨ばった足や48時間の間に肉が溶けてしまった腕が痙攣する中、乱れたベッドの上で、十字架に架かったキリストのグロテスクな姿勢を取った。
この描写を読むだけで、カミュがどれほど心をこめて、子どもの死の場面を詳細に描いているかがわかる。
繰り返すことになるが、オトン判事は主要な人物ではないし、まして彼の子どもは小説の中で何の役割も果たさない。
それにもかかわらず、人の胸を打つ描写が長く続くことは、「大義よりも母を守る」という「愛」のあり方を示している。
アルベール・カミュの作品の全てにはその思想が通底しているし、「反抗」における「連帯」もその一つの現れに他ならない。
ペストは、カリギュラやセルゲイ大公と違い、暗殺できる対象ではない。目に見えない社会通念が人々を自然に動かすように、人々の肉体を攻撃し、死に至らしめる病である。
そのペストに対して、個人が自由であることはできない。個人の自由を行使すれば、ペストは拡散し、終息に向かうことはない。
そうした中で、個人個人が自由でありながら、いかにしてペストに反抗できるのか?
カミュはそこに連帯を見る。自由でありながら、連帯することができれば、ペストを終息に導くことができる。
その根底にあるのは、母というだけではなく、一人一人の人間に対する「愛」がある。
C. 「正午の思想」 — 『反抗的人間』

1951年に出版された『反抗的人間』では、「反抗」と関連がありながら、最終的には対立関係にあるとカミュが考える”革命”や”ニヒリズム”に関して、哲学的で歴史的な考察に数多くのページが割かれている。
その対立の根底にあるのは「過激」と「中庸」の対比。
「反抗的人間」と題された第1章の冒頭から、「過激」を拒否し、「節度」「限界」そして「中庸」を重んじるカミュの立場が明確にされる。
反抗的人間とは何か? それは「ノン(non)」という人間だ。ただし、彼は、拒絶するとしても、断念はしない。彼は最初から、「ウイ(oui)」という人間でもある。一人の奴隷が、一生の間様々な命令を受けてきたが、突然、新しい命令を受け入れられがたいと判断する。その「ノン」の意味は何か?
その意味することは、例えば、「そうしたことが長く続きすぎた」とか、「これまではウイだが、これ以上はノンだ」、「やりすぎ」、さらには、「超えてはならない限度がある」など。結局、その「」ノンは、限度があることの確認となる。反抗的人間の感情の中に見られるのも、限度についての同様の考えだ。他者が自らの権利を「過激化させ」、限界を超えて拡張するとしたら、そこから先にいくと、別の権利が対峙し制限する、というものである。
ここで強調されているのは、長すぎる、やりすぎる、これ以上はダメなど、限度があること。カミュはあえて「過激にする」という言葉を強調し、一方の権利が行きすぎると、他方の権利と対立する状態を際立たせる。
『反抗的人間』で展開される哲学的考察の中で、革命やニヒリズムの歴史的な流れが描き出されるが、それらを一言で言えば、過激な運動ということになる。
そして、そうした過激さは人間の心の奥底に絶えず潜んでいるとカミュは考える。
我々が何をしようとも、過剰さは常に人間の心の中、孤独が宿る場所に居座り続ける。私たちは皆、自らの中に牢獄、罪、荒廃を抱えている。
そうした過激さがもたらす革命やニヒリズムと似ているように見える「反抗」だが、明確な違いがある。「反抗」においては、過激さを廃し、「限度」を尊重する。
人間が存在するためには、反抗する必要がある。その反抗は限度を尊重しなければならない。その限度は反抗が自らの中に見出すもの。そして、その限度の中で、複数の人間が連帯する。そうすることで、彼らは存在を始めるのだ。

個人は自由であるが、他者の自由とぶつかる時には、自由がある程度制約される必要がある。限度を尊重するからこそ、複数の人間の連帯が可能になる。
自由に対する限度を認めた時、個人が複数集まることができ、「我反抗す、故に我らあり」と言うことができるのだ。
「節度と過度」と題された項目では、限度が人間性にとって不可分のものであり、それを無視すると革命のような過ちを招くとされ、その後で以下のように続けられる。
歴史においても、心理学においても、反抗は、調整されていない振り子のようなものであり、深いリズムを探し求めるため、ひどく狂った振幅をする。しかし、その変調が完全ということはなく、一つの軸を中心に行われる。反抗は、人間に共通する本性を示唆する一方で、本性の根本にある「節度」と「限界」を明らかにする。
もし「反抗」の揺れの中心に一つの軸がなければ、それは革命になるだろう。逆に言えば、その軸が、人間の本性を支え、「節度」と「限界」を思い出させる。

こうした考えをカミュは「正午(ミディ)の思想」と表現する。
「ミディ」とは「正午」を意味するが、それと同時に「南フランス」を指す言葉でもある。そして、地中海を連想させる。
その地中海を挟んで、アルジェリアとフランスがある。
カミュはそのどちらにも属しながら、どちらにも完全には属していない。その中間的な存在がカミュであり、彼の「正午(ミディ)の思想」だといえる。
そして、その思想こそが、カミュという作家を、個人的な「不条理」から人々の連帯を促す「反抗」へと向かわせたのだった。
不条理の体験においては、苦しみは個人的なものである。反抗の動きが始まると、苦しみは集合的なものであると意識される。あらゆる人々にかかわる事態になるのだ。違和感に捉えられた精神が最初に行う進歩は、従って、以下のことを認識することだ。つまり、個人が全ての人々と違和感を共有すること。そして、人間の現実が、その全体性において、自己や世界との距離に苦しむこと。一人の人間が感じていた悪が、集合的なペストになる。(中略)我反抗す、故に我らあり。
『反抗的人間』に記されたこの一節は、『異邦人』と『ペスト』の繋がりを示すだけではなく、カミュの思想全体を要約しているとも考えられる。
「不条理」を一人一人の人間が自覚することで、「自由」への欲求が生まれる。その時、自らの自由を求める中、完全なる自由を求めて「過激」になりがちになる。ムルソーが世界に対して違和感を抱いたまま、孤立しているように。
しかし、自らの自由だけではなく他者の自由も認める時、「制限」や「節度」を自覚し、「中庸」の精神が芽生える。他者の自由を尊重することで、「反抗」する中での他者との「連帯」が可能になる。『ペスト』の中で、医師のリユーを始め、タルー、グラン、ランベールたちは、パンデミックに対して集団で対処する。それは、恐怖政治を倒すよりもはるかに困難な「反抗」なのだ。
反抗的人間とは、孤立を脱し、連帯して不条理に立ち向かうムルソーに他ならない。
「中庸」に基づく「正午(ミディ)の思想」はどこから生まれてきたのか?

その根底にあるのは、カミュの抱く「愛」ではないかと考えてみたい。
その「愛」は、「正義よりも母を守る」という言葉によって最も端的に表現されたもの。ただし、対象となるのは母だけではなく、他者でもある。
そこから、他者の自由に対する尊重や自己の自由に対する制限が生じる。過激さが和らぎ、中庸が生まれる。
アルベール・カミュの作品に常に感じられる人間愛は、こうした「正午(ミディ)の思想」によってもたらされる。