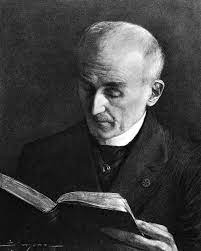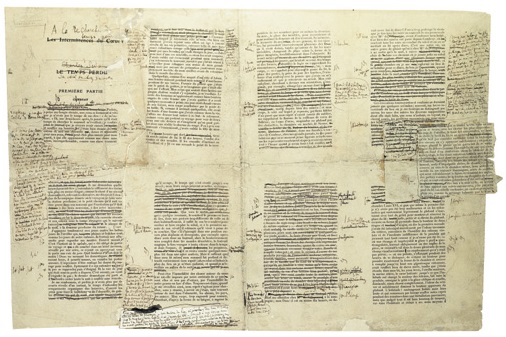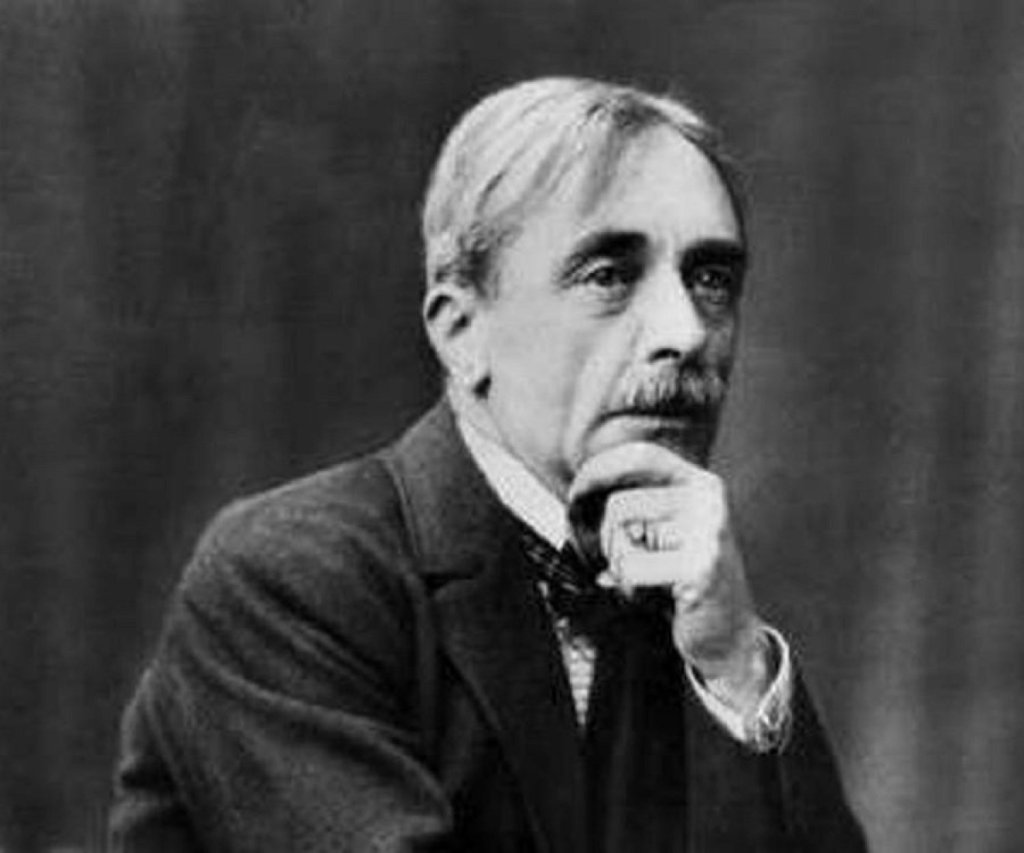
ポール・ヴァレリーは、ステファン・マラルメの弟子であることを自認しており、詩に関する考え方も、コミュニケーション言語と詩的言語を峻別するマラルメ的なものだった。
通常のコミュニケーションにおいては、言語は発信者の意図や思考が受信者にできるかぎりスムーズに伝わることを目指している。
他方、マラルメやヴァレリーの詩を構成する言語では、言葉そのものに焦点が当てられ、詩句の音楽性も手伝って、既存のものとは違う世界像の創造が視野に置かれる。
その結果、マラルメやヴァレリーの詩は、決して読んですっと理解でき、心を動かされる詩ではない。それにもかかわらず、詩句の音楽性によっても、彼らが提示する詩的世界像によっても、高い評価を与えられている。
そうした中で、ヴァレリーが、詩とは何かを私たちに教えてくれる詩がある。それが「シルフ(Le Sylphe)」と題されたソネット(4/4/3/3)。
そこでは、詩(ポエジー)が、風の精(シルフ)の声を通して、「私は・・・」と自らについて語る。

LE SYLPHE
Ni vu ni connu
Je suis le parfum
Vivant et défunt
Dans le vent venu !
Ni vu ni connu
Hasard ou génie ?
À peine venu
La tâche est finie !
Ni lu ni compris ?
Aux meilleurs esprits
Que d’erreurs promises !
Ni vu ni connu,
Le temps d’un sein nu
Entre deux chemises !