
ポール・ヴァレリーが詩のおいて最も重視しているのは、意味と音の連動だった。詩的言語のリズムやハーモニーが生み出す音楽は、単に耳に心地よく響くというだけではなく、日常的に用いられる言語の意味を解体し、より強く感性に働きかけ、精神の活動を活発にする。
言語には感情を動かす力があり、その力は、直接的に意味を伝える実際的な力と混ざり合っている。詩人の義務、仕事、役割は、動かし魅了する力、感情の働きや知的な感受性を刺戟するものを明らかにし、活動させることだ。それらは、通常の言語の使用の中では、ごく当たり前で表面的な生活において使われる記号やコミュニケーションの道具と混同されている。(「ボードレールの状況」)
私たちの日常生活では、言葉は相手に自分の考えや感情を伝えるために使われる。それに対して、詩的言語は「言語の中のもう一つの言語」となり、通常の言語使用では伝えられないものを「暗示」し、人を魔法にかけるような「魅惑」を生み出す。

しかし、そこには危険もある。それが「難解さ」や「わかりにくさ」。
通常の言語では意味ができるかぎり誤解なく伝達される透明性が求められるのに対して、ヴァレリーの構想する詩的言語では、意味が不透明になり、読者は理解するために「努力」が求められるし、努力して解読した意味が正しいとはかぎならない。というよりも、作者が意図した意味が唯一の正解ではなく、多様な意味が読み取られる。
私の詩句は、人々がそれに与える意味を持つ。
(『ヴァリエテ 2』「「魅惑」の注釈」)
意味は最初から決まっているのではなく、言葉が解釈される時点で、読者によって生み出される。そうした考えは、『テル・ケル 1』の中でも再確認される。「作品が現れた時、著者による解釈が、誰であろうと他の人間による別の解釈以上の価値を持つことはない。」
こうした詩的言語観の根底にあるものは、精神の変容する動き(モデュレーション)だろう。ヴァレリーが捉えようとする精神のメカニスムは常に動き、変調を続ける。その動きこそが「生(せい)」であり、言葉の意味も例外ではない。
詩はその動きを固定化させたものではなく、動きを動きとして描き出す。精神がエクササイズする場だといってもいいだろう。
(1)マラルメの弟子
ポール・ヴァレリーは1889年にユイスマンスの『さかさま』を読み、その中に引用されていたマラルメの「エロディアード」の数行の詩句にとりわけ感激する。その熱狂の中でマラルメに手紙を書き、翌年にはパリで詩人と対面し、そして、彼を師と仰ぐ関係は1898年のマラルメの死まで続いた。

『さかさま』に引用されている「エロディアード」の詩句から、私たちは、ヴァレリーがマラルメから何を吸収したのかが見えてくる。
その詩句の中でまず最初に指摘できるのは、自意識のドラマ。エロディアードは、鏡に映る自分に向かい話しかける。それは「自己を見る自己」の姿であり、ヴァレリーが鏡の前のエロディアードの姿と同一化したとすれば、「”自己を見る自己”を見る」というヴァレリー的な意識の基本的な姿勢と対応する。
おお、鏡よ!
倦怠によってお前の額縁の中で凍結される、冷たい水よ、
何度も、何時間もの間も、夢によって
打ちひしがれ、そして、私の思い出を探す、
氷の下、深い穴にある、木の葉ような思い出を、
その私が、お前の中に、自らの姿を現したのです、遠い影のような姿を。
でも、何と恐ろしいこと!幾度もの夜、お前の厳格な泉の中で、
私は、脈絡のない夢の、むき出しの姿を知ったのです!
(マラルメ「エロディアード — 舞台」 v. 44 – v. 51.)
鏡を前にして、「私」は最初に「鏡よ」と呼びかけ、次に「冷たい水」、最後は「厳格な泉」とイメージを変容させながら、様々な連想を繋げていく。その構図は理解できるのだが、これらの詩句が何を意味するのか理解するのは難しい。
鏡を取り囲む額の中、冷たい水が倦怠によって凍結されている。そこに映った鏡像は夢によって打ちひしがれている。そして、「私」は思い出を探すのだが、その思い出は、深い穴の中で「お前」の氷の下にある木の葉のようだと言われる。
「私」は鏡の中の自らの姿を見て、遠い影のようだと思う。そして、「私」の脈絡のない夢のむき出しの姿を知ったのだという。
これらの言葉の直接的な意味はなんとか理解できる。しかし、この一節をどのように解釈し、何が伝われば理解したといえるのか? 読者は様々な思考を巡らせることになる。
こうした詩的言語について、マラルメ自身は、次のように表現した。
私が「花!」と言う。すると、私の声が輪郭を遠ざける忘却の外に、これまで知られていた萼(がく)とは別の何かが、音楽的に立ち上がる。観念そのものであり、甘美な、そして、あらゆる花束に不在の花だ。(「詩の危機」)

通常のコミュニケーション言語では、「ハナ」という音声を聞いたり、「花」という文字を見れば、花のことだと理解される。その際、意味の伝達が阻害されることはない。
反対に、詩の言葉は、既存の意味を伝えるためにあるのではなく、それまで知られていた花とは違う花、「あらゆる花束に不在の花」を音楽的に立ち上がらせるものだと、マラルメは言う。
「エロディアード」を例に取ると、鏡の前に座る女性が鏡の中の自分の姿に話かけるという状況を伝えれば、通常の言語活動の目的は達する。その意味の伝達にできるかぎりノイズが入らないことが、コミュニケーションをスムーズにするポイントとなる。

それに対して、鏡が冷たい水と表現され、倦怠によって凍り付くという言葉が続くと、そこには大きなノイズが発生し、意味の理解が妨害される。しかしその一方で、その詩句から、それまでは不在だった意味が出現する可能性もある。つまり、それらの言葉に出会う以前には鏡という言葉は鏡という意味しか指示しなかったが、今後は水や倦怠を連想させるようになる。そのようにして、新たな意味が生成する。
こうしたマラルメの言語観からさらに一歩進め、ヴァレリーは詩的言語から生まれる意味の個別性に考えを進める。
つまり、一般化された意味があるわけではなく、言葉を読み取る一人一人によって異なった意味が生まれる。例えば、「氷の下、深い穴にある、木の葉ような思い出」という詩句から読み取る意味や、そこから連想するものは、それぞれの読者によって異なったものになる。そして、そこにこそ詩的言語の魅力がある、とヴァレリーは考えたに違いない。
マラルメの言葉が他の人々の中に作り出すことができる魅力は、言語の性質そのものにより、数多くの思い違いや誤解を含んでいることにある。それらは必要不可欠なものであって、たとえ著者の思考の直接的で完全な伝達が可能だとしても、そうした伝達は、芸術の最も美しい効果を除去し、消滅させてしまうことになる。(『ヴァリエテ 2』「マラルメについての手紙」)
マラルメの詩句の最も美しい効果は、「花」という言葉が花という意味を伝えるだけであれば、失われてしまう。その反対に、思い違いや誤解だと普通は思われる理解が、詩的効果をもたらす上で必要なものとされる。
こうした考えは非論理的、あるいは逆説的に思われる。しかし、言葉は元来の意味が通じれば役割を終えるのではなく、読む度毎に様々な意味が生成する可能性が、詩的言語の働きだとすれば、決して逆説とはいえないし、論理的な思考に基づいているといえる。
言葉と意味の関係は決して固定したものではなく、常に流動している。こうした詩的言語観が、マラルメからヴァレリーへと伝えられたのだった。
(2)アナロジー(類推)
人間が生きている限り精神は変容を続ける。若きパルクであれば、今まさに身体の感覚に目覚めようとする精神が、一夜の間、転調する。「海辺の墓地」の「私」であれば、現実を流れる時間と永遠への思いの中で葛藤する精神が、風の立つ気配を身体が感じ取るまでの間、転調を繰り返す。
そうした転調の原理となるものがあるのだろうか?

ヴァレリーが感激したマラルメの「エロディアード」の詩句が、その原理を私たちに教えてくれる。
エロディアードは、最初に「鏡よ」と呼びかけ、次に「冷たい水」、次に「厳格な泉」と、同じ対象に対して異なった呼びかけをし、その都度イメージを変容させていった。
その変容の原理として働くのは、「アナロジー(類推)」だといえる。
「海辺の墓地」の最初の詩句と最終第144行目の詩句を並べると、愚直といっていいほどのアナロジーが用いられ、その役割が明らかになる。
この静かな屋根、そこでは鳩が動き回る(v. 1)
この静かな屋根、そこでは三角帆の小舟が餌をついばむ(v. 144)
(「海辺の墓地」)
静かな屋根の上に、一方では鳩が、他方では小舟が見える。しかも、小舟はあたかも鳩のように餌をついばんでいる。そのようにして、鳩と小舟の類似が作り出され、その連想を通して、船の浮かぶはずの海と屋根とのアナロジーが暗示される。そして、いつしか屋根が海へと変容する。

そのように考えると、変容が第一詩節の中ですでに行われていたことに気付くことになる。第144行目の詩句はその変容の確認だと考えてもいいだろう。(第1詩行の訳は、詩句の構文を考え、上の訳とは語順を変更した。)
鳩の動き回る、この静かな屋根が、
松の木の間で、どきどきと鼓動する、墓の間で。
正確に正午が、太陽の炎で構成するのは、
海、常に新しく始まる海!
おお、思考の後で報いとなるのは、
神々の静寂を、長く見ることだ! (「海辺の墓地」v. 1 – 6)
この詩節からは、屋根が海の隠喩であることはまだそれほどはっきりとわからないかもしれない。つまり、屋根と海の類似が明確に示されてはいない。
屋根には、鼓動する命の流れがある。それに対して、海には、正午の太陽が照りつけ、波が常に反復し、不動を思わせる。そのために、屋根と海は対照を成すようでもある。
しかし、屋根の側には死を連想させる墓があり、海は常に新しく始まるという動きを感じさせ、静と動が交差している。さらに、屋根の静かさと神々の静寂が静かな海を連想させる。
このようにして、これらの言葉の連なりが、屋根と海のアナロジーを作り出す働きをするのだと考えることができる。
こうしたアナロジーについて、ヴァレリーは次のような思考を巡らせたことがある。
アナロジーとは、イメージを変化させる能力であり、イメージを結び付け、一つのイメージの部分と他のイメージの部分を共存させ、意図的であろうとなかろうと、それらの構造のつながりを発見する能力なのだ。そうしたことは、イメージの場である精神を描写不可能なものにしてしまう。言葉はそこで効力を失う。そこでこそ、言葉が形成され、精神の目の前に湧き上がってくるのだ。私たちに言葉を描くのは、精神なのだ。(「レオナルド・ダ・ビンチの方法序説」)

アナロジーがイメージを変化させる機能であるとしたら、一つのイメージを別のイメージへと変調する際に働く原理がアナロジーだといえる。その原理に基づき、鏡が冷たい水になり、屋根が海になる。
そして、その原理が働く時、精神の中で、言葉とイメージの関係が変化する。
イメージが生起する場としての精神の中で、従来のイメージを形作ってきた言葉はそれまでの意味を失う。その意味で、精神は描写不可能になる。
その一方で、変容に伴い、精神の中には新たな言葉が形成され、浮かび上がってくる。それらの言葉は、類似に基づいて変容される新たなイメージを描き出す。精神が私たちに言葉を描くとは、そうした現象を指すのだと考えられる。
既存の言葉が精神を描くのではなく、精神が言葉を描き、その言葉がイメージを生成させる。そのようにして生成したイメージは、生(せい)の流れの中で変容する。アナロジーはその変容を導く主要な原理だと考えることができる。
(3)エクササイズとダンス
ヴァレリーは、言葉の意味が固定したものではなく流動性を持つという考えを、書く次元にも適応した。
私はこうした奇妙な考察に導かれ、書くという行為に対して、純粋な「エクササイズ」の価値しか認めないようになった。(『ヴァリエテ 2』「マラルメについての手紙」)
エクササイズとは、最終的な行為ではなく、目的に到達するための練習や訓練といった意味であり、一端書き終わった詩句にも、次の機会にはまた手を入れるかもしれない。その意味で最終段階は常に先延ばしされ、すでに書かれた詩句もその時点での完成品にすぎない。
「若きパルク」は執筆の開始から公表までに約4年の歳月がかかったが、詩の冒頭に置かれたアンドレ・ジッドへの献辞の中で「エクササイズ」という言葉を使い、その詩が「完成」段階にあるというよりも、「過程」であることが示されている。
何年も前から、/私は詩作を放棄していました。/再び自らにそれを強いるように試み、/創作したこのエクササイズを、/あなたに捧げます。/1917年 (「若きパルク」)
ポール・ヴァレリーの詩人としての評価を一気に高めた「若きパルク」も、彼にとっては言語活動の一つの過程でしかないことが、「エクササイズ」という言葉によって示されていると考えていいだろう
もし公表された詩句に詩人が手を加えられることがないとしても、読者が詩句にもたらす「思い違いや誤解」が、詩句の意味を更新していく。そして、その更新は終着点がなく、潜在的な可能性として常に残されている。
そのように考えると、ヴァレリーの考える詩的言語は、ある一つの意味を伝えるという目的に向かって進む直線的な動きをするのではなく、その都度の意味を生成しながら反復する円環運動を思わせないだろう。
日常言語が目的地に達することを目指す「歩行」だとすると、詩的言語はその場で踊る「ダンス」だといってもいい。

ヴァレリーによれば、歩行は「目的を持った外的な行動」だが、人間にはそうした行動とは別のタイプの行動があり、ダンスはその中の一つの形だということになる。
子どもや犬が飛び上がったり、跳ね回ったりすることは、「歩行のための歩行」「水泳のための水泳」であり、目的は、感情をエネルギーによって変え、その感情のある状態を作ることになる。(中略)
私たちの力を費やす素晴らしい形が存在する。それは、発散する動きを秩序付けたり、組織化したりする。(中略)
ダンスの喜びは、その回りに、ダンスを見る喜びを発散させる。(『ドガ、ダンス、デッサン』)
歩行は目的が到達できれば意味を失う。しかし、ダンスの動きは、それ自体が目的であり、一つの意味が伝達されたからといって、ダンスの意義が失われることはない。観客は、ダンサーの身体の動きを観賞し、その美しさに魅了される。
詩の言葉も同様であり、ある意味が伝わったからといって、存在意義がなくなるわけではない。詩の言葉はそこに残り続け、読者を魅惑する。詩は言葉のダンスなのだ。
その際、ダンスであるかぎり、子どもや犬の跳躍とは違い、ある効果を生み出すために言葉が秩序づけられ、組織化されたエクササイズでなければならない。ヴァレリーはそのように考えていたのではないかと思われる。

その意味で、彼は、ボードレールやマラルメの流れの中にあり、インスピレーションを重視するのではなく、詩法(ポエチック)を重視した。その際に彼らが根拠としたのはエドガー・ポーだった。
ポーは『構成の原理』の中で、自作の詩「大鴉」について解説しながら、次のように述べている。
私が証明しようと意図したのは、詩の構成に関するいかなる点も偶然や直感に帰属することはできないということ、そして、この作品(「大鴉」)が一歩づつ結論の方に歩んでいったのは、数学の問題の厳密で論理的な正確さを伴ってだった、ということだ。(エドガー・ポー著、シャルル・ボードレール訳「構成の方法」)
ヴァレリーであれば、単なる跳躍ではなく、ダンスにするためには、数学的な厳密さに基づく構成が必要だと言うだろう。
それがあって始めて、見る喜びが生まれ、人々を魅了することができるダンスになる。
そのダンスは決して一度踊られたら忘れられてしまうものではなく、何度でも踊られうる。その意味では、一回一回は完成していながら、同時にエクササイズ的な側面も持っているといえる。
その意味でも、ポール・ヴァレリーの詩は、言葉のダンスと呼ぶにふさわしい。

ポール・ヴァレリーは、自分の中を覗き込み、「自己を見る自己を見る」という姿勢の中で、精神のメカニスムの解明を目指した。そこで彼の眼に映ったのは、常に変容する「生(せい)」の動きだったにちがいない。
風が立つ、生きようと試みなければならない。(「海辺の墓地」)
この有名な詩句で言われる「生きる」という言葉は、止まっているように見えるもの、それらを固定化させる枠組みも、実は全てが動き続け、生き続けているのであり、その動きに気付き、その動きに参加しなければならない、ということだろう。
そのことは、時計によって計測される抽象的な単位としての時間と、私たちが実感として感じる持続との関係を考えると、わかりやすいかもしれない。私たちが生きる時間は、固定されたものではなく、体感として感じるものなのだ。
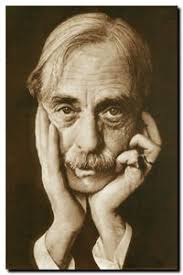
ヴァレリーが精神のメカニスムを解明しようとし、詩という言葉によるダンスによって描き出そうとしたのは、そうした「生(せい)」の動きだといえる。
私たち読者も、その言葉のダンスに加わり、コミュニケーション言語を通して伝達される特定の意味を探すのではなく、なんらかの意味の生成に参加することが求められる。
その際にキーワードとなるのはアナロジー。言葉の響き合うハーモニーに耳を傾けながら、一つのイメージが暗示する類似したイメージへと変容する姿をたどっていくことで、ヴァレリーの言葉たちが作り出す魅惑を感じ取ることができるだろう。
『ヴァレリー詩集』鈴木信太郎訳、岩波文庫。
ポール・ヴァレリー『若きパルク、魅惑』中井久夫訳、みすず書房。
ポール・ヴァレリー『レオナルド・ダ・ヴィンチ論』塚本昌則訳、 ちくま学芸文庫。
山田直 『ヴァレリー 人と思想』 清水書院。
清水徹 『ヴァレリー 知性と感性の相克』 岩波新書。