私たちは、宗教は慈愛をもたらし、人々に平穏を与えるものだと、漠然と信じている。しかし、現実の世界に目を向ければ、キリスト教圏とイスラム教圏の対立は激しく、宗教的な衝突が戦争やテロを引き起こしている。歴史を振り返っても、キリスト教の内部ではカトリックとプロテスタントの間に殺戮があり、ユダヤ教徒への迫害も繰り返されてきた。現代のイスラム教においても、シーア派(イランなど)とスンニ派(サウジアラビアなど)の対立は続いている。
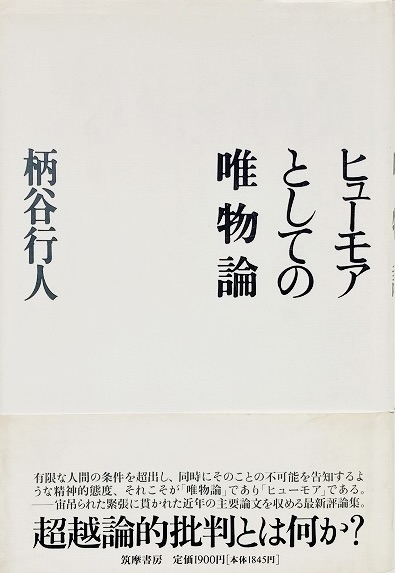
こうした現実を前にすると、「愛」を説くはずの宗教が、なぜ争いを生み出してしまうのかという問いがどうしても浮かんできてしまう。私自身、この疑問を長く抱いてきたが、柄谷行人による伊藤仁斎論を読んでいて、一つの答えに出会った。
柄谷が解説する儒学者・伊藤仁斎(1627-1705)の思想は、「私」と「あなた」という対の関係を出発点にしていて、その関係を一般化・抽象化することを拒む。ここに重要な視点がある。以下の引用を読んでいくと、宗教が実際の殺戮を抑止する方向に働かない理由が見えてくる。
仁とは愛であり、愛は「実徳」である。つまり、愛は、対関係においてのみある。それゆえに「実徳」なのだ。朱子は、仁を「愛の理」、すなわち愛の本質または本質的な愛とみなす。
(柄谷行人『ヒューモアとしての唯物論』「伊藤仁斎論」、p. 224.)
「仁」の意味する「愛」とは、「他者への思いやりとか情け」と言い換えることができる。そして重要なのは、その愛の対象が具体的な「他者」であるという点である。「愛は、対関係においてのみある」という言葉は、そのことを示しており、だからこそ「実徳」、すなわち実のある徳となる。
これに対して、中国南宋の儒学者であり朱子学の創始者である朱子(1130-1200)は、「愛」を具体的な対関係から切り離し、抽象化した。そうして導かれたのが一般的な「愛」という概念であり、それが「愛の理」、すなわち愛の理念である。
ここで、「具体」と「一般」の違いが問題となる。私たちはしばしば、一般が本質的であり、具体は単なる個別例にすぎないと考えがちである。そして「本質」を追い求めようとする。たとえば化学実験を思い浮かべれば、一回一回の実験結果から科学的に正しいとされる法則を導き出し、その法則が正しい答えとして認められる。その過程では、個々の差異は捨象され、重要視されない。
この観点から見ると、伊藤仁斎があくまで具体的な対関係にこだわった理由と、朱子が抽象的な愛の本質を説いたこととの違いが、より鮮明に理解できるだろう。
その後、柄谷は「実」と「理」の区別を改めて確認した上で、「愛の理」を追求することは、対関係における愛を失わせるだけではなく、反作用として他者への残酷さや非情さを生み出すと指摘する。そしてその例として、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』に登場するイワン・カラマーゾフの言葉を引用している。
「天地の間唯一の実理のみ」と仁斎がいうとき、この「実理」も「実徳」と同様に、対関係の現実性を意味している。それをはなれた「理」や「徳」は、空疎であるばかりか「残忍刻薄」に転化する。われわれは、これを朱子学に固有の道徳的リゴリズム(丸山眞男)などと考えてはならない。たとえば、イワン・カラマーゾフは次のようにいっている。
「僕はお前に一つ、白状しなければならないことがある。一体どうして「近きもの」を愛することができるんだろう?僕は何としても合点がゆかないよ。僕の考えでは「近きもの」だからこそ愛することができないので、「遠きもの」こそはじめて愛されうるんだと思う。隣人を愛しうるのは抽象的な場合に限る。どうかすると、遠方から愛しうる場合もある。しかし傍へ寄ってはほとんど不可能だ。」(ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』米川正夫訳)
熱烈に神や人類や真理を愛する者こそ、近くにある”他者”を愛しえない。前者の愛は、一般的な他者との関係における愛、したがって「愛の理」としての仁であり、後者の愛は、対関係としての愛である。神や人類を愛する者は、具体的・現実的な他者を平然と切りすることができる。それが「残忍刻薄」にほかならない。
(同上、pp. 224-225)
「残忍刻薄」、すなわち残酷で薄情であることは、道徳的な厳格さの結果ではなく、対関係の喪失から生じる。言い換えれば、「理」が「実」を失わせるのである。
イワン・カラマーゾフが対比する「近きもの」と「遠きもの」も、この「実」と「理」の対比に重なる。
イワンは「隣人を愛しうるのは抽象的な場合に限る」と言うが、その「隣人」とは抽象化された存在であり、目の前にいる具体的な「この人」ではない。さらに彼は「遠方から愛しうる場合もある。しかし傍へ寄ってはほとんど不可能だ」と言葉を続ける。
柄谷の読み取る伊藤仁斎の思想は、この指摘をさらに一歩進める。すなわち、近くの他者を愛することは不可能であるだけでなく、「愛の理」を追求すればするほど、近くの他者を切り離し、残酷になりうるというのである。
「熱烈に神や人類や真理を愛する者こそ、近くにある”他者”を愛しえない。」「神や人類を愛する者は、具体的・現実的な他者を平然と切りすることができる。」
宗教の違いによる対立がますます激しくなる現代の現実を前にするとき、この言葉は「宗教は平和をもたらすのか」という問いに対する、一つの答えとなる。
仁斎がいいたいのは、「『仁』の完全型」をめざすこと、それ自体が反対に「残忍刻薄」に転化するということなのだ。そして、これは朱子学に固有なものでもないし、孔子以後に生じたものでもない。孔子が「仁遠からんや」というのは、すでに仁が高遠なものであるという考えが支配的だったことを意味するのである。
(同上、p. 225)
戦争という大義の名の下では、殺人は英雄的な行為へと変貌する。普段であれば「残忍刻薄」とみなされる行為が、あまりにも容易に正当化されてしまう。人類愛を掲げる者たちでさえ、目の前の殺戮を一刻も早く止めようと訴えるのではなく、「正義の戦いが勝利するまで戦いをやめるべきではない」と主張したりする。そのとき「仁が高遠なもの」とされることが、実は具体的な対関係における残忍さを支えているのではないか。
柄谷の伊藤仁斎論のこの一節を前にして、そんな思いを抱くことになる。
ここで浮かび上がるのは、宗教や理想主義的な思想が人々を導くとき、その「普遍性」や「理念」そのものが暴力を支える契機となる可能性があるという逆説である。人類愛、正義、平和といった高遠な言葉は、現実の対関係を超えて響く力を持つために、時として「この人」を顧みない冷酷さを生む。言い換えれば、抽象化された「理」は、具体的な「実」を切り捨てる危険を常にはらんでいる。
もしそうであるならば、宗教や倫理を問い直す契機は、理念の普遍性をさらに高めることではなく、むしろ「私」と「あなた」の関係に立ち返ることにあるだろう。隣にいる具体的な他者への思いやり、その対関係の現実性に根ざした「仁」をどう回復できるのか。その問いかけが、宗教が平和をもたらしうるための出発点ではないかだろうか。