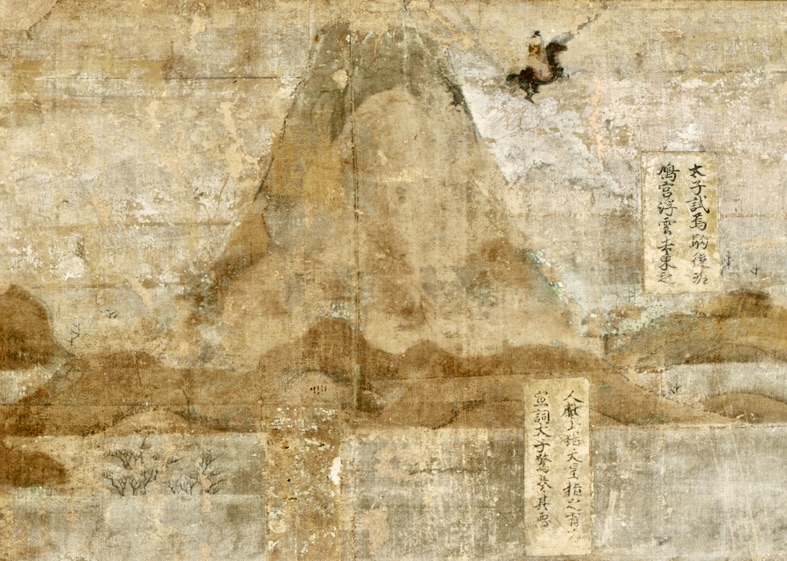(2)日本文学の中の言葉

「言葉には届かない領域がある」という言語観を、荘子と仏教の公案を通して確かめてきたが、ここからは、その意識が、理論や説話ではなく、和歌や俳句といった言語芸術によってどのように表現されてきたのかを、簡単に見ていこう。
和歌の場合は三十一音、俳句ではわずか十七音によって、言葉の直接的な意味だけではとうてい表現不可能な世界が浮かび上がる。そこでは、言葉は常に意味を超えたものを思わせ、「そこにあるもの」から、その奥にひっそりとたたずむ何かを呼び起こす。

その代表的な例の一つとして、まずは藤原定家のよく知られた和歌を読んでみよう。
見渡せば 花も紅葉も なかりけり
浦の苫屋(とまや)の 秋の夕暮
(『新古今和歌集』秋上・363)
秋の夕暮れ、浜辺に立ち、ぐるりとあたりを見渡しても、美しい花も紅葉した木々もない。目に入ってくるのは、浦に建つ漁民の粗末な苫屋だけである。
和歌の意味するところを散文で言い表せば、そのような寂しく殺風景な情景への言及にすぎない。
しかし、それにもかかわらず、この和歌は日本的な美の表現としてしばしば取り上げられ、現代の私たちの感性にも強く訴えかける力を持っている。
その一つの鍵は、「なかりけり」という言葉にある。
この語が存在を否定することによって、かえってその侘しく寂しい光景の中に、存在しないはずの花と紅葉が一瞬、心に描き出される。