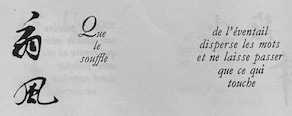ボードレールはエドガー・ポーの影響を強く受け、アメリカの詩人の詩や詩論を積極的に翻訳し、19世紀後半の文学に大きなインパクトを与えた。マラルメはその洗礼を真正面から受けた詩人であり、ポーの詩を英語で読むために、イギリスに留学したと言われることもある。
その二人の詩人が、ポーの代表的な韻文詩「大鴉(The Raven)」を訳している。
もちろん、マラルメはボードレールの翻訳を参照しながら、自分の訳文を構成しただろう。ポーの原詩の横にボードレールの訳を置き、必死に自分なりの訳を考えている姿を想像してみると、急にマラルメに親しみが湧いてきたりする。
ここでは、18の詩節で構成される「大鴉」の第1詩節を取り上げ、ポーの原文とボードレール、マラルメのフランス語訳を比較して読んでいこう。
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore—
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
“Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door—
Only this and nothing more.”
Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C’est quelque visiteur, — murmurai-je, — qui frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela, et rien de plus. » (Baudelaire)
Une fois, par un minuit lugubre, tandis que je m’appesantissais, faible et fatigué, sur maint curieux et bizarre volume de savoir oublié — tandis que je dodelinais la tête, somnolant presque : soudain se fit un heurt, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre — cela seul et rien de plus. (Mallarmé)
続きを読む →