
プルーストと言えば、紅茶に浸したマドレーヌが過去の思い出を甦らせるというエピソードが語られるほど、マドレーヌと記憶の関係はよく知られている。
また、『失われた時を求めて』の解説などを読むと、「無意志的記憶」や「心の間歇」といった表現をよく目にする。
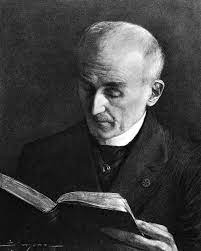
しかし、記憶の問題はプルースト特有のものではない。
哲学の分野では、アンリ・ベルクソンの『物質と記憶』が1897年に出版されている。ベルクソンはその中で、物質の「知覚」ではなく、「記憶」に焦点を当て、外的現象と精神の交差するところに生まれるイメージを問題にした。

文学の分野では、「フロベールの”文体”について」(1920)という雑誌記事の中で、プルースト自身が、「記憶の現象」を作品の構成原理として用いた作家として、シャトーブリアンとジェラール・ド・ネルヴァルの名前を挙げている。二人の作家の作品では、物語の流れの中で突然記憶が甦り、それが新たな展開のきっかけとなる技法が用いられることがった。
とりわけネルヴァルの「シルヴィ」に関しては、「心の間歇(Intermittances du cœur)」という題名を付けてもいいとさえプルーストは言う。(”間歇”と訳したintermittanceという言葉は、”一時的に中断する”とか”断続”といった意味。)
プルーストは、先行するこうした思想や文学作品を前提としながら、最初は「心の間歇」という総題を考えた作品である『失われた時を求めて』を創作する中で、「記憶」を人間の「生(せい)」の中核に位置づけたのだった。
マドレーヌのエピソードもそうした視点から理解することが求められるし、一見無関係に思われるが、作品の中でしばしば語られる絵画、音楽、文学についての考察に関しても、「記憶」の働きと同様に理解することができる。

