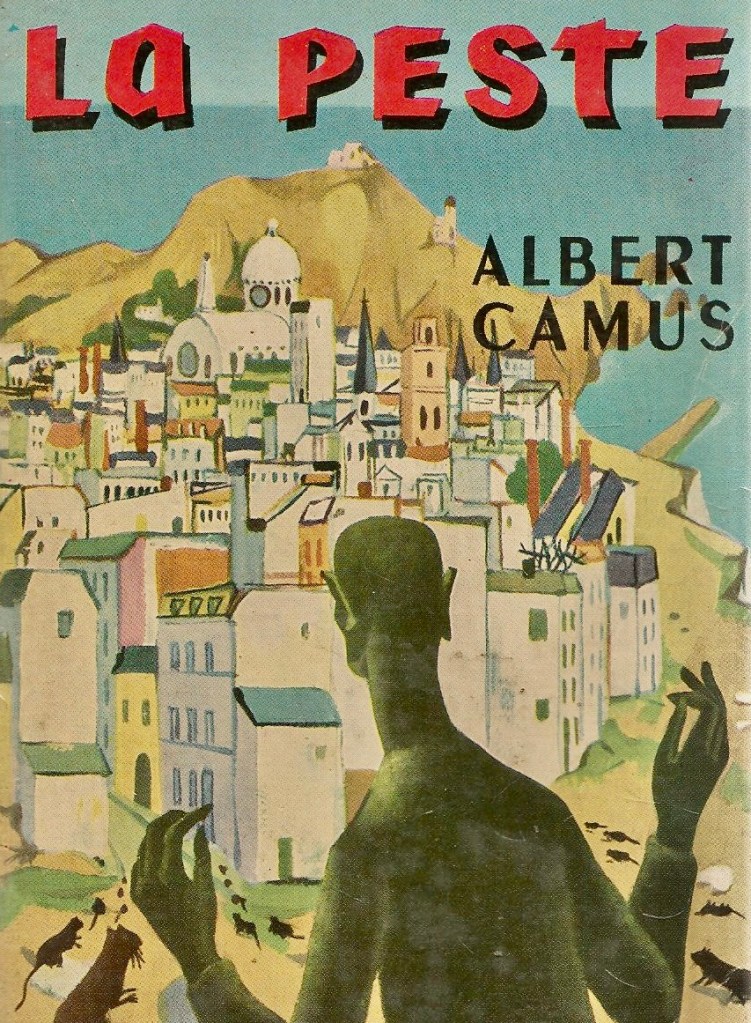
アルベール・カミュが1947年に出版した『ペスト』は、アルジェリアのオラン市を舞台にし、ペストが一つの町を外部の世界から隔離し、人々の生活を一変させてしまう様子をドキュメンタリー風に描いた小説。
実際、人類の歴史の中で、ペストは人間に何度も大きな災禍となってきた。カミュがそうした歴史を参照したことは確かだ。
それと同時に、この小説の中で、ペストはナチス・ドイツの象徴でもあった。そのことは、カミュ自身が証言している。
疫病と戦争には自然災害か人災かという違いはある。しかし、一般市民に甚大な被害をもたらすという点においては変わりがない。
ここでは、市中に広がる不安な病について、最初に「ペスト」という言葉が使われた時の記述をたどり、カミュがペストと戦争をどのようなものだと捉えていたのか探っていこう。
最初に出てくるベルナール・リューは、ペストに罹った多くの患者の治療にあたる医師であり、また、出来事の推移を綴る語り手でもある。彼は「私」という代名詞を使わず、三人称を使うことで客観的な視点を確保し、ペストの発生から収束までを年代記風に語っていく。
Le mot de « peste » venait d’être prononcé pour la première fois. A ce point du récit qui laisse Bernard Rieux derrière sa fenêtre, on permettra au narrateur de justifier l’incertitude et la surprise du docteur, puisque, avec des nuances, sa réaction fut celle de la plupart de nos concitoyens. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils vous tombent sur la tête.
「ペスト」という言葉が初めて口にされた。ベルナール・リューを部屋の窓辺に残したままにしている物語のこの時点において、語り手にはリュー医師が感じている不確かさや驚きを正当化することが許されるだろう。そいうのも、いくつかの微妙な点は違っていても、彼の反応は大部分の市民たちと同じものだったからだ。様々な災害は確かにみんなに共通のものだが、しかし、突然自分に降りかかると、なかなかそれを信じられないものだ。
流行し始めた病気の兆候を前にして、医師は不確かさ(l’incertitude)や驚き(la surprise)に捕らわれる。
不確かさとは、病がペストかどうか確認が持てないということであり、驚きとは、もしそれがペストだったらという驚き。それらは、普通では考えられないことを前にした時、誰もが持つ感情だといえる。
大きな災害が起こるとは誰も思っていない。そのために、「突然自分に降りかかると(ils vous tombent sur la tête)、なかなかそれを信じられない(on croit difficilement aux fléaux)」。
しかも、大きな災禍がこれまでにも至るところで起こってきたにもかかわらず、実際に起こると、信じられないことが起こったと思う。その例として、語り手はペストと戦争を挙げる。
Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu, comme l’étaient nos concitoyens, et c’est ainsi qu’il faut comprendre ses hésitations. C’est ainsi qu’il faut comprendre aussi qu’il fut partagé entre l’inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent : « Ça ne durera pas, c’est trop bête. » Et sans doute une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l’empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours, on s’en apercevrait si l’on ne pensait pas toujours à soi.
この世界には、戦争と同じくらい多くのペストがあった。それにもかかわらず、人々は、ペストや戦争の時、常に自分が無防備でいることに気付く。リュー医師は市民たちと同じように無防備だった。そんな風に、彼のためらいを理解する必要がある。そんな風に、彼が不安と信頼の間で揺れていたのを理解する必要がある。戦争が起こると、人々はこう言う。「そんなには続かないだろう。あまりにも愚かなことなのだから。」確かに戦争はあまりにも愚かだ。しかし、だからといって、戦争が続かないことはない。愚かさは持続し続ける。自分のことをいつも考えているというのでなければ、そのことに気付くのだが。
無防備でいる(dépourvu)とは、準備ができていないこと。予想していないのだから、準備もしていない。また、予想外のことが起こっているのかどうかとためらう(ses hésitations)ことも自然だし、それが本当に起こったかもしれないという不安(l’inquiétude)と、そんなことが起こるはずがないという信頼(la confiance)の間で揺れる(être partagé)ことも、ごく自然な心理状態だといえる。
戦争が勃発する(une guerre éclate)と、最初はみんな「そんなには続かないだろう(Ça ne durera pas)と思う。「あまりにも愚かなこと(c’est trop bête)」だからだ。
その言葉は、カミュが戦争をどのように捉えていたかをはっきりと示している。あまりにも愚か(trop bête)なことなのだ。
しかし、悲しいことに、それが起こり、しかも長く続いてしまうという現実がある。ウクライナやパレスチナの状況は、まさにそれを証明している。
なぜそんなことになってしまうのか?
語り手は、その理由を、人間はいつも自分のことを考えているからだと推測する。
もし自分のことをいつも考えているというのでなければ(si l’on ne pensait pas toujours à soi)、戦争は愚かなことであり、しかも、その愚かさが持続するということに気付くはずなのだ。
次の一節では、「自分のことを考える」ことがどういうことか、オランの市民たちを例として説明される。
Nos concitoyens à cet égard, étaient comme tout le monde, ils pensaient à eux-mêmes, autrement dit ils étaient humanistes : ils ne croyaient pas aux fléaux. Le fléau n’est pas à la mesure de l’homme, on se dit donc que le fléau est irréel, c’est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours et, de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu, parce qu’ils n’ont pas pris leurs précautions.
その点に関して、市民たちは他の人々と同じだった。彼らも自分のことを考えていた。別の言葉で言えば、彼らはヒューマニストだった。つまり、彼らは災害を信じていなかった。災害というものは人間の力では測ることができない。だから、それは現実的ではないと思ってしまう。すぐに通り過ぎてしまう悪夢なのだ。しかし、いつも通り過ぎていくわけではない。悪夢から悪夢へと続く中で、去って行くのは人間なのだ。しかも、最初に去るのはヒューマニスト。彼らは備えをしなかったからだ。
ヒューマニスト(humaniste)という言葉は、基本的には、ルネサンスの時代の人文主義者、つまり、ギリシア・ローマの古典文芸を元に人間性の本質を研究した知識人たちを指す。しかし、ここでは、人間愛を持った人といった意味で使われている。
オランの市民たちが「自分のことを考える」というのは、自分を基準にして全てを判断するということ。彼らはヒューマニストであり、自分たちが想像できないような限度を超えた愚かなことが起こるなどと想像することはない
他方、災害は人間の力で測ることができない(Le fléau n’est pas à la mesure de l’homme)。
だからこそ、大災害が起こっても、現実とは思えず(irréel)、悪夢(un mauvais rêve)でしかない。そして、現実的な対処ができず、悪夢はすぐに終わるだろうと思ってしまう。
そのために、自分の尺度で考えるヒューマストたちは、準備ができていず(dépourvu)、災害が終わる前に、自分たちが消え去ってしまう。
そうした人間のあり方はとりわけ批難すべきものではないが、しかし、謙虚さが欠けていると語り手は続ける。
Nos concitoyens n’étaient pas plus coupables que d’autres, ils oubliaient d’être modestes, voilà tout, et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l’avenir, les déplacements et les discussions ? Ils se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu’il y aura des fléaux.
市民たちが他の人々より罪があるというわけではなかった。謙虚であることを忘れていた。それだけだ。彼らには全てが可能だと考えていた。その考えが前提としていたのは、災害は不可能だということだった。商売を続けていたし、旅行の準備もしていた。いろいろな意見も持っていた。そうした中で、どうやってペストを想像できただろう。ペストは、未来も、移動も、議論も消滅させてしまうのだ。彼らは自分たちが自由だと思っていた。しかし、災害があるかぎり、誰一人決して自由ではない。
ヒューマニストとして人間性を信頼し、人間的な尺度で判断するかぎり、全てのことが人間にとって可能(possible)であり、その場合には、尺度を超えた災害は、起こるはずのない不可能なこと(impossible)だと思われる。
そして、通常の生活を続け、将来(l’avenir)において不測の事態、たとえばペストに襲われ、通常の生活が不可能になるなどとは想像しない。
オランの市民たちはそのように考え、自分たちが自由だと思っていた( Ils se croyaient libres)。実際、全てが可能だと思うことは、自由であると思うことと同じことだ。
しかし、大災害が起こってしまえば、誰一人自由ではいられない。それは、ペストにおいても、戦争においても同じこと。
こう言ってよければ、「あまりも馬鹿げたこと」は、人間から自由を奪う。
災害があるかぎり、誰一人決して自由ではない(personne ne sera jamais libre tant qu’il y aura des fléaux)。
実際に災害を体験したことがある人間であれば、誰もがこの言葉に納得するだろう。
こうした考察の後からも、リュー医師はペストの状況について様々に考えていくのだが、最後にめまい(vertige)に捕らわれる。
Mais ce vertige ne tenait pas devant la raison. Il est vrai que le mot de « peste » avait été prononcé, et il est vrai qu’à la minute même le fléau secouait et jetait à terre une ou deux victimes. Mais quoi, cela pouvait s’arrêter. Ce qu’il fallait faire, c’était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qui convenaient. Ensuite, la peste s’arrêterait parce que la peste ne s’imaginait pas ou s’imaginait faussement. Si elle s’arrêtait, et c’était le plus probable, tout irait bien. Dans le cas contraire, on saurait ce qu’elle était et s’il n’y avait pas moyen de s’en arranger d’abord pour la vaincre ensuite.
しかし、そのめまいは理性の前では続かなかった。実際、「ペスト」という言葉がすでに口にされていた。実際、その時には、疫病が一人か二人の犠牲者を揺すり、地面に倒していた。しかし、それだとしても、疫病が収まる可能性もあった。実際にする必要があったのは、認識すべきものをはっきりと認識し、無益な影を追い払い、それにふさわしい対策を取ることだった。その後になれば、ペストが収まるかもしれない。というのも、ペストとは想像できなかったし、あるいは誤ってペストと思ったのかもしれない。もしそれが収まれば、そして、その可能性が大だったが、全てはうまくいくだろう。そうでない場合でも、ペストが何かを知り、最初はまず何とか対処し、次にペストに打ち勝つ方法がないかどうか探ることになるだろう。
語り手が口にする「理性(la raison)」という言葉は、アルベール・カミュの人生哲学の根本にあるものを示している。
彼にとって、「あまりにも馬鹿げたこと」に直面した際に最も必要とされるものは、ヒューマニズムではなく、理性なのだ。
理性を働かせ、認識すべきものをはっきりと認識する(reconnaître clairement ce qui devait être reconnu)。例えば、病がペストであるながら、ペストであることを明確にすること。病のために犠牲者(victimes)が出ているのであれば、その状況をしっかりと把握すること。
現実に起こっていることでないことを想像して、怯えたり、偽りの情報を流したりしないこと。つまり、無益な影を追い払うこと(chasser les ombres inutiles)。
実際の状況にふさわしい対策を取ること(prendre les mesures qui convenaient)。
こうした指摘は、様々な災害や大きな事件が起こる度にフェイクニュースが拡散される現在の状況にも当てはまる。事実を確認することなく自分が信じたい情報を信じ、それを拡散する。
そうした時にこそ、「理性」を働かせることが必要になる。
誰も自分が理性的ではないと思っていない。むしろ理性を働かせていると思っているからこそ、ある情報を信じ、それを同胞たちと共有しようとする。
それは、カミュの時代も現代も同じことだ。
そうした状況を理解していると思われる語り手は、「確かさ」がどこにあるかを示そうとする。
Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de la ville s’enfla d’un coup. D’un atelier voisin montait le sifflement bref et répété d’une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude, dans le travail de tous les jours. Le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants, on ne pouvait s’y arrêter. L’essentiel était de bien faire son métier.
医師が窓を開けると、町の騒音が一気に大きくなった。隣の工房からは、機械式こぎりの短く来る返される音が上ってきていた。リューは身体を震わせてた。そこには確かさがあった。、日々の仕事の中だ。それ以外のことは細い糸や無意味な動きにすぎず、そこに留まることはできなかった。大切なことは、自分の仕事をしっかりとこなすことだった。
めまいにとらわれていたリューが部屋の窓を開けると、隣の工房から機械式のこぎりの音が聞こえてくる。語り手は、その音に象徴される日々の仕事(le travail de tous les jours)の中にこそ、確かさ( la certitude)があると言う。
そして、最後にこう付け加える。
「大切なことは、自分の仕事をしっかりとこなすことだった。(L’essentiel était de bien faire son métier)」
カミュにとって、理性を働かせるとは、何か特別なことを考えたり行動したりすることではなく、日々にしている目の前のことを、普段通りにすることなのだ。
リューの場合であれば、医師として、患者の症状を確認し、オラン市全体の状況を把握し、その場にふさわしい対策を考え、仲間たちと共同して治療にあたること。
その普通のことが、ペストという恐ろしい伝染病に襲われた時には、最も困難なことになる。リューも多くの死に立ち会い、ペストが終息しようとする最後になって、心を通じ合わせてきた友人の死に立ち会い、別の町で療養していた妻が死んでいたという知らせを受け取る。
「あまりにも馬鹿げたこと」の中で、普通でいることは、何よりも難しい。
そうした中で、自分の仕事をしっかりとこなすように導いてくれるのが、「理性」なのだ。

「大切なことは、自分の仕事をしっかりとこなすことだった」という言葉は、18世紀の思想家ヴォルテールの哲学的風刺物語「カンディード」を思わせる。
この世では全てが最善に整えられているという教えを受けたカンディードには、その教えとは反対に、最悪のことしか起こらない。
物語の最後になり、「全ての出来事は可能世界中の最善の世界の中でつながっている」というパングロス先生に対して、カンディッドはこう応える。「でも、私たちの庭を耕さなければなりません(il faut cultiver notre jardin)。」
哲学的な楽天主義を信じることではなく、自分の庭を耕すことが、幸福への道なのだ。
(参照:ヴォルテール 『カンディード』 地上における幸福に向けて)

『ペスト』のベルナール・リューが幸福なのかどうかはわからない。しかし、彼が自分の庭を耕し、自分の仕事をしっかりとこなしたことは、疑う余地がない。
そのリューの姿を通して、アルベール・カミュは、人間の尺度では測ることができない大災害や戦争に際して、私たち一人一人がどのように生きるべきかを具体的に描いたのだった。
ヒューマニスト的にではなく、理性を指針にして自分の仕事をこなす。「あまりも馬鹿げたこと」のまっただ中で、そうした姿勢を保つことは難しい。しかし、難しければ難しいだけ、そうすることが大切なこと(L’essentiel)なのだ。
1947年に出版された『ペスト』を2024年に読み返した時、私はそうしたメッセージをカミュから伝えられた。