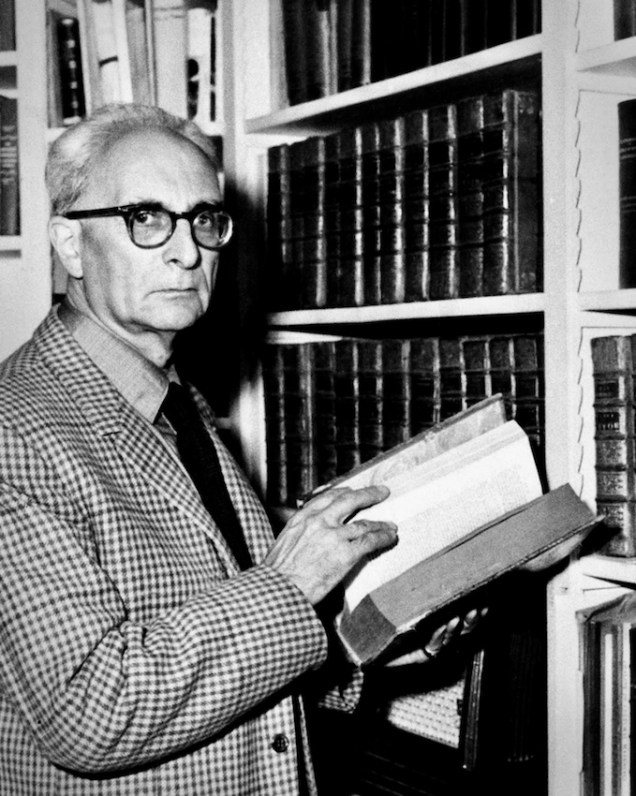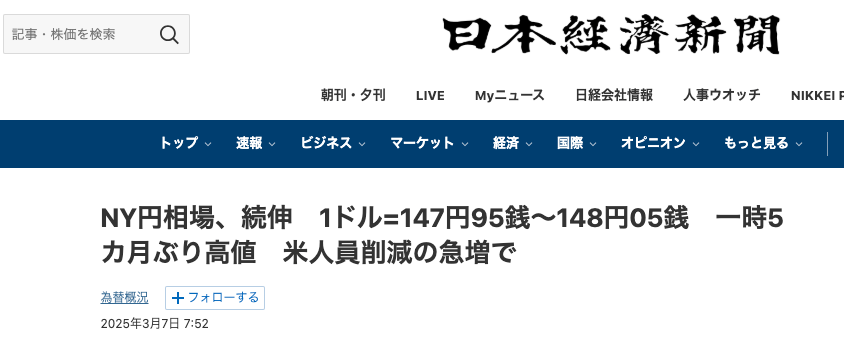(1/2の続き)
具体的事象の論理(「弱い歴史」)と論理的性質(「強い歴史」)が矛盾するなかで、「歴史」にアプローチするにはどのようにしたらいいのか?
Par rapport à chaque domaine d’histoire auquel il renonce, le choix relatif de l’historien n’est jamais qu’entre une histoire qui apprend plus et explique moins, et une histoire qui explique plus et apprend moins. Et s’il veut échapper au dilemme, son seul recours sera de sortir de l’histoire : soit par en bas, si la recherche de l’information l’entraîne de la considération des groupes à celle des individus, puis à leurs motivations, qui relèvent de leur histoire personnelle et de leur tempérament c’est-à-dire d’un domaine infra-historique où règnent la psychologie et la physiologie ; soit par en haut, si le besoin de comprendre l’incite à replacer l’histoire dans la préhistoire, et celle-ci dans l’évolution générale des êtres organisés qui ne s’explique elle-même qu’en termes de biologie, de géologie, et finalement de cosmologie.
歴史家があきらめる各歴史領域との関係において、歴史家の相対的な選択は、より多くを学ぶが説明力の乏しい歴史と、説明は多いが学びの少ない歴史との間で行われるしかない。もしこのジレンマから逃れようとするなら、唯一の方法は歴史の外に出ることである。下方から出る場合、情報の探求は歴史家を集団の考察から個人の考察へ、さらに個人の動機の分析へと導く。その動機は、個人の歴史や気質に関わるものであり、心理学や生理学が支配する下位歴史領域に属する。上方から出る場合、歴史家は理解の必要性から歴史を先史時代に置き直し、さらに先史時代を有機的存在の一般的変化の文脈に置き直すことになる。その一般的変化の説明は、生物学・地質学、そして最終的には宇宙論の用語によって行われる。
続きを読む