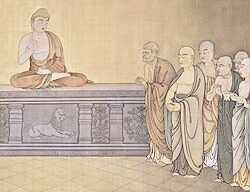日本は言うまでもなく、フランス本国においてさえ、フランス・ロマン主義文学に親しむ人は今ではごく少数になっている。サント・ブーヴ(Sainte-Beuve)の詩を読む人となると、なおさら少ないだろう。
そうした中で、彼の代表的な韻文詩の一つとはいえ、なぜ「黄色い光線(Les Rayons jaunes)」を取り上げるのかと、少し意外に思われるかもしれない。
今回この詩を取り上げるのは、その主題である「黄色(jaune)」という色が、現代人の心の動きとどこかで重なって見えるからだ。
ネット社会の中で、私たちは日々、多くの情報に囲まれて過ごしている。その流れに身を任せながら、ときどき理由もよく分からないまま、ふと気持ちが沈むことがある。何かを信じたいと思いながら、どこかで信じきれない気持ちが残る。楽しい時間を過ごしているはずなのに、それをあらかじめ「思い出作り」と言葉にしてしまう。そうした感覚に、心当たりのある人も少なくないのではないだろうか。
「黄色い光線」は一八二九年に発表された詩で、今からおよそ二百年前の作品である。それでも、この詩には、時代を超えて今の日本人の感覚にそっと触れてくる何かがあるように思われる。
そのことは、詩の冒頭に置かれたエピグラフからも感じ取れる。そこには、古代ローマの詩人ルクレティウスの『物の本質について』から、「さらに、あらゆるものは陰鬱で不気味な様相を帯びてくる」という一節が引かれている。
この言葉は、サント・ブーヴの詩の世界に静かな陰影を与えると同時に、読む側の心にもゆっくりと染み込んでくるように思われる。
また、せっかくフランス語で詩を読むのだから、その形式にも目を向けておきたい。
一つの詩節は六行からなり、最初の二行は十二音節、三行目は六音節である。続く三行も同様に、十二音節の二行と六音節の一行が反復される。
韻の構成は、最初の二行が平韻(AA)で、次の四行は抱擁韻(BCCB)となっている。
このように形式が非常に整っているので、フランス語詩特有の音とリズムの美しさを感じ取ることができる。
Les Rayons jaunes
Les dimanches d’été, le soir, vers les six heures,
Quand le peuple empressé déserte ses demeures
Et va s’ébattre aux champs,
Ma persienne fermée, assis à ma fenêtre,
Je regarde d’en haut passer et disparaître
Joyeux bourgeois, marchands,
続きを読む →