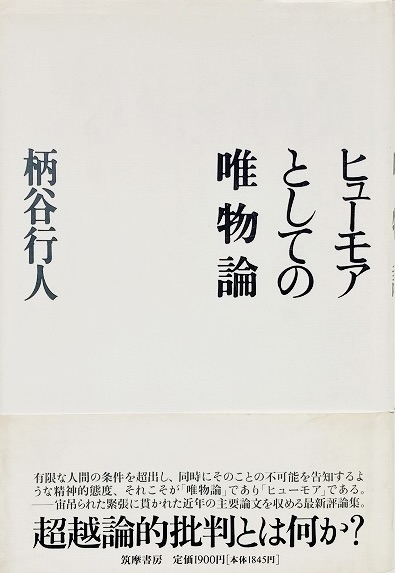ジェラール・ド・ネルヴァルは、目の前の現実を明晰な意識で観察し、そこから出発して、繊細な感受性と幅広い知識に支えられた、音楽性豊かな詩的散文によって独自の文学世界を築き上げた。このことは、「夢と幻想の作家」という先入観を外せば、誰にでも見えてくるだろう。
『東方紀行』(Voyage en Orient)の「ドリューズたちとマロニットたち」(Druses et Maronites)の章には、「朝と夕べ」(Le Matin et le Soir)と題された一節がある。その冒頭では、イタリアの詩人ホラティウスの詩句と、オリエントの船乗りの歌う民謡の一節が掲げられており、そうした詩や歌の調べに呼応するかのように、ネルヴァルの文も音楽性に満ちた詩的散文となっている。
Que dirons-nous de la jeunesse, ô mon ami ! Nous en avons passé les plus vives ardeurs, il ne nous convient plus d’en parler qu’avec modestie, et cependant à peine l’avons-nous connue ! à peine avons-nous compris qu’il fallait en arriver bientôt à chanter pour nous-mêmes l’ode d’Horace : Eheu ! fugaces, Posthume… si peu de temps après l’avoir expliquée… Ah ! l’étude nous a pris nos plus beaux instants ! Le grand résultat de tant d’efforts perdus, que de pouvoir, par exemple, comme je l’ai fait ce matin, comprendre le sens d’un chant grec qui résonnait à mes oreilles sortant de la bouche avinée d’un matelot levantin :
Ne kalimèra ! ne orà kali !
( Gérard de Nerval, Voyage en Orient, « Druses et Maronites », Le Prisonnier, I. Le matin et le Soir.)
続きを読む →