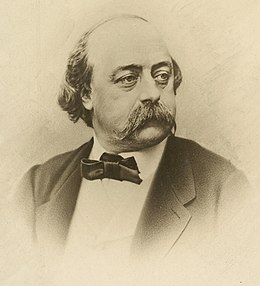
『ボヴァリー夫人』の「現実」は、現実の社会を「再現」した「コピー」ではなく、フロベールが幾何学的な精密さをもって「創造」した「新しい現実」あるいは「もう一つの現実」に他ならない。
それは架空の存在だが、しかし人間の生きる実際の現実の「典型」として、読者に「現実の効果」を感じさせるものになっている。
その効果の大きさ、つまり小説の中に作り出された社会のリアルさは、『ボヴァリー夫人』が公共の秩序を乱すという罪状で裁判にかけられたことによって、それ以上にない仕方で証明されている。
フロベールの言葉に、それだけ力があったということだ。
では、どのような現実が提示されているのだろう?
登場人物たちが生きるのは、19世紀半ばの市民社会。そこを支配するのは資本であり、人々は社会規範を遵守し、良識を持って生きることが求められた。悪徳や情念は偽善によって隠されている。
ロマン主義的魂を体現するエンマは、そうした規範に違反する存在であり、葛藤の末、死に至る。
『ボヴァリー夫人』が、エンマの夫シャルルの学校時代から始まり、薬剤師オメの叙勲で幕を閉じるのは、小説内に広がる市民社会を読者に実感させるために他ならない。
19世紀フランスの市民社会
A. シャルルとオメ
シャルル・ボヴァリーとオメは市民社会を生きる典型的な人物である。
しかし、二人には大きな違いもある。シャルルは現状に自足しているが、オメは社会的な上昇を望んでいる。そして、資本主義社会において生き残るのは、オメ型の人間である。
小説は次の一節で始まる。
ぼくたちは復習室にいた。その時、校長先生が入って来た。後ろにはブルジョワ風の服を着た「新入生」。その後には用務員さんがいて、大きな勉強机を運んでいた。眠っている生徒たちは目を覚まし、一人一人立ち上がった。勉強中にびっくりしたという風に。

この新入生がシャルルだが、彼を最初に特徴付けるのは「ブルジョワ風の服」。
その服は、シャルルがブルジョワ階級に属していることを示している。
実際、シャルルの父は元軍医補で、母親は豊かなメリヤス雑貨商の娘。後に学校を卒業後、シャルルは大学で医学を勉強し、開業医の免許試験に合格して、トストという田舎の町で開業する。従って、田舎ではあってもブルジョワ階級に属しているといえる。
その一方で、他の生徒たちが着ている制服を着ていないことで、その場で浮く存在であることが暗示されてもいる。
次の節では、シャルルは「田舎の少年」であると明記される。そして、都会であるルーアンの学校に入学した「新入生」が笑いの対象になる場面が続く。

「立ちなさい。」と先生が言った。
彼は立った。帽子が落ちた。クラス中が笑い始めた。
彼は身をかがめて拾った。隣の生徒が肘で叩いて、帽子を落とさせた。彼はもう一度拾った。
「ヘルメットを片付けなさい。」と先生。彼は気の利いた人なのだ。
生徒たちが大爆笑し、哀れな少年は混乱した。帽子を手に持っていたらいいのか、床に置けばいいのか、頭に被っていればいいのか、わからなかった。もう一度腰掛け、帽子を膝の上に置いた。
「立ちなさい。」と先生。「名前を言いなさい。」
新入生は、もごもごとよくわからない名前を発した。
「もう一度!」
同じようにもごもごした音が聞こえ、クラス中からからかう声が上がった。
「もっと大きな声で!」と先生が叫んだ。「もっと大きな声で!」
新入生は、これ以上ないといった決心をし、大きく口を開け、胸から一気に空気を吐き出して、誰かを呼ぶ時のように、あの名前を言い放った。「シャルボヴァリ。」
可哀想なシャルルは、みんなの笑い者になり、自分の名前さえまともに言えない。
この状態はエンマとの結婚後も続き、エンマの視線で捉えられるシャルルは凡庸で、出世欲がなく、つまらない夫だと見られ続ける。
そのために、シャルルについて語る後の時代の読者たちも、シャルルに対して断定的に凡庸という言葉を投げつけ、彼との結婚生活が退屈なためにエンマは不倫に走ったといった説明がなされることも多い。『ボヴァリー夫人』を世界10大小説の一つとするサマセット・モームは、シャルルを「面白くもおかしくもないアホな男」と決めつけている。
彼はブルジョワ階級には属しているが、その中の「負け組」のように見える。

こうしたシャルルに対して、オメは「勝ち組」だといえる。その象徴が、小説の最後に、エンマやシャルルと何の関係もない彼の受勲の知らせが告げられることである。
ボヴァリーの死後、三人の医者がヨンヴィルの町にやって来たが、誰も成功しなかった。オメーが彼等をすぐに打ち負かしたからだ。彼は恐ろしいほどのお客を獲得している。行政が彼を優遇し、世間も彼を守っている。
彼は、最近、勲章を受章した。
オメは好ましい人物として描かれてはいない。
ボヴァリー夫妻にとっては親切そうでありながら、シャルルに無理な手術をするように勧めたり、エンマの二度の不倫のきっかけを作ったりもする。小さな噓は平気で、エンマが彼の店のヒ素を飲んで自殺したことを隠すためなら、砒素と砂糖を間違えたなどという噂を広める。

しかし、こうした偽善は、資本主義社会に中における必要悪のようなものかもしれない。つまり、「勝ち組」になるために必要な小さな悪。
フロベールは、オメの精神性が18世紀の哲学から来ていることを、オメの口から語らせている。
彼は、「至高存在」を信じ、理性に基づいた自然宗教の信奉者であるという自覚を持ち、「私の神、私のあがめる神は、ソクラテス、フランクリン、ヴォルテール、ベランジェの神! 私は『サヴォワの助任司祭の信仰告白』と同じ立場に立ち、89年(革命)の不朽の綱領に賛成する人間だ!」と宣言する。
この精神が革命を起こす起爆剤となり、貴族の時代を市民の時代へと変革した核となった。そして、19世紀の合理主義精神に基づくエネルギー革命の根底を支え、資本主義社会の中で文明の進歩をもたらすものだった。
オメは彼が生きる時代の精神を体現する存在であり、当時の田舎のブルジョワの典型的人物である。
従順に従う妻と薄汚れて躾のあまりよくない4人の子どもを養い、薬剤師の仕事で少しでも多く稼ぎ、できれば名誉を得たいとも願う。そのために、コレラの予防をするための活動をしたり、公益に寄与する著作を自費出版したり、権力者にすり寄ることもする。
勲章を受章するという最後は、オメの体現する合理主義、実証主義精神が、彼らが生きる時代精神と合致し、そのために「勝ち組」になる可能性があることを示している。

ところで、オメ受勲のエピソードはフロベールが小説の執筆の最後の時期に付け加えたもの。それ以前は、シャルルとエンマの一人娘ベルトが、シャルルの死後、伯母さんのもとに送られ、さらには工場労働者になるエピソードで終わるものだった。
全ての物が売り払われた後で、残ったのは12フラン75サンチームだけだった。そのお金は、ボヴァリー嬢が祖母のところに行く旅費として使われた。おばあさんはその年に亡くなった。ルオー爺さんは体が麻痺していたので、一人の叔母が彼女を引き取った。叔母は貧しく、生活費を稼ぐために、彼女を製糸工場に行かせた。
ブルジョワ階級に属していた娘が労働者階級に転落するこの最後は、当時の状況からすると大変にリアルだと感じられたに違いない。
しかし、それではシャルルの負け組性を強調するばかりになってしまう。
それに対して、オメの受勲を最後に置けば、ブルジョワ社会における「勝ち負け」を皮肉に浮き上がらせ、社会の現実をより全体的に浮き上がらせることなる。
B. マルクスとダーウィン
『ボヴァリー夫人』の中のブルジョワたちが生きる社会の状況を理解するために、ここでマルクスとダーウィンを取り上げてみたい。

カール・マルクスは1818年生まれで、フロベールやボードレールとほぼ同世代だといえる。
彼はプロイセン王国で生まれたが、後に国籍を捨て、1849年以降はイギリスを中心に活動した。
そうした中でとりわけ注目したいことは、1848年に起こった2月革命の最中にパリを訪れ、共産主義者同盟の中央委員会を創設したこと。そして、1852年には、『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』を出版し、共和制を崩壊させ帝政を成立させたナポレオン3世を攻撃したことである。
フローベルが『ボヴァリー夫人』を執筆した1851年末から1856年にかけては、まさにナポレオン3世の帝政が始まった時期だった。
革命とか階級闘争といった政治的な視点を抜きにし、マルクスを初めとする社会主義者たちの思想を大まかにまとめれば、資本主義の進展によって資本を持つブルジョワ階級と貧困に落ち込む労働者たちの格差が拡大する中で、労働者階級を含めた全ての人々の平等と権利を認める社会を目指すものと言うことができるだろう。
マルクスがエンゲルスと共に執筆した1847年の『共産党宣言』では、社会を資本家階級(ブルジョワ)と労働者階級(プロレタリアート)の階級対立によって特徴づけ、最終的に階級対立は解消され、一人の人間の自由な発展が、万人の自由な発展の条件となるような協同社会が生まれることを目指すとしている。
こうしたマルクス主義思想は、彼らの時代に資本主義社会がどれだけ強固なものになっていたかを、逆説的な形で証明している。
『ボヴァリー夫人』の中では、シャルルやオメの他に、服地商人のルルが、資本主義を代表する人物として登場する。
彼はエンマに、婦人物の珍しい品、旅行鞄、マント、レースなどを売りつけ、手形を使い借金地獄に追い込む。そして、借金の形に家を取るなどして金をもうけ、最後は乗合馬車屋を始める。
ルルは、オメのように名誉を求めることなく、金銭だけの獲得を目指すという意味で、資本主義の申し子といってもいいだろう。
フロベールが小説の中に作り出した社会には、マルクスやフランスの社会主義者たちの影は見えない。しかし、ブルジョワによって労働者が搾取されているという彼らの告発を知れば知るほど、ブルジョワ社会のあり様を理解することになる。
そこで生き延びるためには、オメやルルである必要がある。
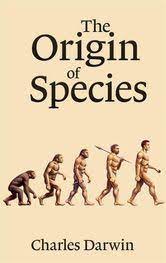
そのことをはっきりと教えてくれるのが、ダーウィンの進化論であり、その理論の中核をなす自然選択説である。
チャールズ・ダーウィンは、1859年に出版した『種の起源』の中で、全ての生物種は共通の祖先から出発し、自然選択の過程を通して変化を続けているという、生物進化論を発表した。
その発想を思いついたのは、マルサスの『人口論』を読み、ある状況下において好ましい変異は保存され、好ましからぬものは消滅される傾向があり、状況に適応したものから新しい種が形成されることを学んだ時だった。
その考えをベースとして、同一種においても、限られた環境の中で生存競争が起き、生存に有利な個体はその性質を子孫に伝え、不利な性質を持った個体は生殖が不利になり、子孫を残せないようになるとした。
自然選択とは、自然環境が、個体あるいは種の環境への適応能力に応じて選択をし、強い者が残し、弱い者は消滅するという生物学の理論である。
こうしたダーウィンの進化論のベースには、合理主義精神に基づく進歩思想があり、時代を経るに従って技術が発展することを当然と見なす科学主義がある。
興味深いのは、マルクスとダーウィンがともに科学主義精神に則って思考を進めたことである。
自然淘汰は強者の生存を可能にし、環境に適応したものだけが生き残り、新しい種を生み出す。従って、最新の種が最も適応したものだといえる。生物で言えば、進化の最先端にいるのは人間ということになる。
マルクス主義においては、現状は資本家の支配が続いているが、しかし階級闘争を通して到達するのは、私有財産の否定による完全平等の実現である。その意味で、パラダイスは未来に置かれている。
こうした進歩意識は、キリスト教において、楽園がアダムとイブの追放以前に置かれていることを比較するとわかりやすいだろう。キリスト教では、パラダイスは時間を遡った世界の起源にある。
マルクスとダーウィンの思想が19世紀の市民社会の時代精神であり、『ボヴァリー夫人』の「現実」を通底しているとすると、エンマをはじめ全ての登場人物は、資本主義社会の中で生存競争を繰り広げていることになる。
地方都市のブルジョワたちの姿は、ノルマンディー地方ではなく、フランシュ・コンテ地方ではあるが、ギュスターヴ・クールベが1849年に発表した「オルナンの埋葬」に、美化することなく、ありのままの姿で描かれている。

エンマの黒い怒り —— ロマン主義の刷新

こうした市民社会では、良識を持ち、教会に通い、社会の規範から逸脱しない生活態度が求められる。不倫などもってのほか。
しかし、エンマのロマン主義的魂は、彼女を規範の枠外に連れ出してしまう。そのために、日常生活に満足できず、夫以外の男の愛を求め、手形を切ってまで買い物をし、身の破滅を招くことになる。
A. 『ボヴァリー夫人』裁判
そうしたエンマの振る舞いは、市民社会の倫理から見れば愚かで断罪に値する。としたら、読者はシャルルを悪し様に言うのではなく、エンマや小説の不道徳性を非難するか、あるいは無視し、社会から排除すればいいだけのはず。
しかし、実際には、『ボヴァリー夫人』は裁判にかけられ、公の場で取り上げられた。発売直後から爆発的にヒットしたのは、裁判で知名度が上がったことによる。

裁判で小説を断罪する側は、次のような問題点を数え上げた。
ー「良き趣味』に反し,道徳的な感性を傷つける描写がある。
ー社会の根底である結婚制度に背反する不倫を肯定するかのような、良俗に反する主張が見られる。
ー宗教の尊厳を犯す部分がある。
ー「写実主義文学」の烙印を押すのが相応しい。問題は、人間の情念を描くこと自体ではなく、愛欲や憎悪を無制限、無軌道に描くこと。「一切の衣服を脱ぎ捨てる女性」のように、規範のない芸術は芸術ではない。
ー『ボヴァリー夫人』には、公衆の儀礼という規範が欠如している。
弁護する側もこれらの点を認めた上で、フロベールの意図は、現実生活から小説のテーマを取り上げ、ブルジョワ階級の真の典型を創造し,「有益な結果」に到達することだという論陣を張った。つまり、悪徳を嫌悪させることで美徳へと導く意図があり、道徳的で宗教的な思想が込められているというのである。
この弁護はあまり説得力があるとは言えないが、しかし、判決は無罪となる。
判決文からすると、裁判官の作品自体に対する評価は検事と変わらない。
作者はエンマの性格を誇張し、自己を尊重する作家であれば守べき規範があるにもかかわらず、その規範を逸脱するという過ちを犯し、「卑俗かつ不快なる写実主義」を浸透させた。従って、『ボヴァリー夫人』は厳格な非難に値する。
無罪になるのは、弁護側がフロベール家の社会的な地位を強調し、その戦略が成功したからだった。
判決では、作品に非難が向かっても、作家に対しては、「多年に渡る真摯な労苦」に言及され、倫理違反に当たる箇所は「数量的に、違犯容疑に十分該当するものとは認めがたい」とされた。
裁判の判事、弁護士、裁判官たちの評価から垣間見えることは、エンマが不道徳で非難すべき行動をとり、社会の規範から逸脱する女性であるにもかかわらず、読者を遠ざけるどころか、魅力的であり、彼女を真似る人間が出てくる可能性を考えているということである。魅力がなければ、誰も彼女を理解しようなどとは思わない。
B. 一切の衣服を脱ぎ捨てる女性
19世紀の半ばに美術の世界で美意識が変化しようとしていたことも、エンマ的なものの受容を促しただろう。
検事の求刑の中に、「一切の衣服を脱ぎ捨てる女性のように、規範のない芸術は芸術ではない」という表現がある。
では、芸術のおいて服を脱ぎ捨てた女性、つまりヌードの規範とはなにだろ?
西欧ではルネサンスの時代以来、女性のヌードが美の表現として受け入れられる伝統があり、決してスキャンダラスなものではなかった。
ところが、1860年代になり、エドワード・モネの描く裸婦像がスキャンダルを巻き起こす。
同じ女性の裸体を描いたものでありながら、一方は美の表現として、他方は猥褻なものと見なされる。
その違いは、21世紀の私たちにはわかりずらいかもしれない。
まず、1863年のサロンで賞賛の的となった絵画と、サロンに落選した絵画を見てみよう。


アレクサンドル・カバネルの「ヴィーナスの誕生」は、描かれた対象がヴィーナスという神話的存在というだけではなく、肉体のリアルな感触が表現されず、理想化されている。そうした描き方をすることによって、女性が現実の存在ではなく、理想の存在となり、官能的な印象を与えない。それが絵画を見る作法だった。

それに対して、エドゥアール・マネの「草上の昼食」の女性は、スキャンダルを引き起こした。構図はルネサンスの画家ティチアーノの有名な「田園の奏楽」を下敷きにしている一方、肉のたるみや筋肉の筋が描かれ、奥にいる女性は下着さえ身につけている。
実際にはシャンゼリゼの森で服を着た男性とピクニックをする女性がオール・ヌードでいることなどあり得ない。それにもかかわらず、この絵画は現実の情景とみなされ、風紀に反するものとして非難された。
マネが2年後にサロンに出品した「オランピア」も、構図はティチアーノの「ウルビノのヴィーナス」に依拠しているが、マネの裸婦は女神ではなく、現実の女性、しかも娼婦であろうことが、描き方によって伝えられている。ベットの上で眠る犬は貞節を象徴するが、尾を立てたクロネコは性的イメージと捉えられる。その結果、この絵画は、「草上の昼食」以上のスキャンダルを巻き起こすことになった。



こうしたマネの絵画は、裸婦をリアルに描くという意味では写実主義の絵画と見なされる可能性もあるが、しかし古典絵画を裸体画を典拠とした時点で、美の創造を目指したはずである。
そのことは、リアリズムを代表するクールベの裸婦像との比較を通して感じ取ることができるだろう。「画家のアトリエ」では、女性は現実の場面にいるモデルであり、肉体は美化されることなくリアルに再現されている。
それに対して、エドゥアール・マネは、ヨーロッパ絵画の美の伝統の中にリアルさを注入し、美の新しい表現を模索したといえるだろう。
フロベールが『ボヴァリー夫人』の中に現実以上にリアルな「現実」を作り上げ、その中にエンマを置いたことは、マネと同様、新しい時代における新しい美の表現を目指していたことを示している。
そして、そこで彼が考えたことは、「ロマン主義の刷新」だった。
C. エンマの「黒い怒り」

ロマン主義的な美について思い出しておくと、現実を喪失の時と見なし、今ここにないもの、例えば、現在に対する思い出、都市に対する自然、物質世界(肉体)に対する内的世界(心)に到達したいと熱望するところから生まれた。
その構図は、時間の経過とともに全てが過ぎ去ってしまう現実世界において、永遠の世界にあるイデアへと愛の力で向かっていこうとする、プラトニスムと対応している。

しばしば「ボヴァリスム」と呼ばれる、「現実と夢との不釣り合いから幻影を抱く精神状態」あるいは「夢と現実の相剋に悩む性癖」とは、従って、ロマン主義精神そのものだということになる。
19世紀前半のロマン主義の時代には、決して到達できない理想を憧れることで陥るメランコリックな精神状態が抒情性の源となり、美的表現を生み出した。
19世紀半ばからは、市民社会の実証主義精神がより強く浸透し、ロマン主義的魂は、非現実な夢を追いかける無益な存在として、功利主義的精神から揶揄される対象になる。
このように考えると、エンマが遅れてきたロマン主義者であることがはっきりする。
修道院で少女時代を過ごしたエンマは、母の死を聞き、ただ悲しむだけではなく、ロマン主義を代表するラマルティーヌの詩句を思い、うっとりとする。
母が死んだ時、彼女は最初の幾日かひどく泣いた。死んだ母の髪の毛を使って、死者を思い出すための品を作ってもらった。(父のいる)ベルトに送った手紙は人生に対する悲観的な考えで満ちていたが、その中で、自分が死んだら同じ墓に葬って欲しいと頼んだ。お人よしの男(父)は彼女を病気だと思い、会いに来た。エンマは心の中で満足していた。最初の一撃で、青ざめた人生の滅多にない理想に到達したと感じていた。平凡な心の人間がそこに到達することなど決してない。彼女はラマルティーヌ的な心の蛇行にずるずると滑り込み、湖の上のハープの音色、今にも息の絶えそうな白鳥の全ての歌、枯葉の落ちる全ての音、天空に昇る純粋な乙女達、谷間を駆け巡る永遠の声を聴いた。
エンマにとって、母の死は人間の生命の儚さを思わせるきっかけに過ぎない。「死んだ母の髪の毛」は、思い出の品となり、決して到達できない母への想いを募らせる。こうしてプラトニスム的構図が出来上がる。

彼女はそこで、凡庸な人々には決して到達できない「青ざめた人生の滅多にない理想」を知ったように思い、「ラマルティーヌ的な心の蛇行」に滑り込み、「永遠の声」を聴く。
19世紀前半であれば、こうしたエンマの気質は、ロマン主義的抒情を生み出す美しい魂と見なされたはずである。
しかし、この一節にはどこか皮肉があり、母の死を抒情のきっかけとしてしまうことに違和感を感じさせる語りがなされている。実際、「永遠の声」の後には、次のような一文が続く。
彼女はそうしたものに退屈した。それらを認めたくなかったのだ。しかし習慣で、その後からは虚栄心のために、同じようにしていた。そして最後には、自分の心が穏やかになっているのを感じて驚いた。心に感じている悲しみは、額の皺の数より多くはなかった。
フロベールは若い頃から、ある状況になると誰もが口にしてしまう型にはまった表現から距離を置き、紋切り型を揶揄していた。
ここでは、ロマン主義の紋切り型に対して「彼女は退屈した」と続けることで、明確な皮肉を飛ばしている。
「心に感じている悲しみは、額の皺の数より多くはなかった。」この比喩には、いかにもフロベールらしい、ユーモアの混ざった皮肉が感じられる。
この後、エンマの気質がさらに明確に描き出される。
彼女の精神は、熱狂のただ中にありながら現実的。教会が好きなのは花のため、音楽はロマンスの歌詞のため、文学は情熱的な興奮のためだった。彼女の精神は、信仰の神秘を前にすれば反抗し、規律に対してはさらに苛立った。規律には彼女の体質に対して反感を引き起こす何かがあったのだ。父親が彼女を寄宿から引き取った時、立ち去るのを残念に思う人はいなかった。修道女長は、最近になってエンマは共同体に対して敬意を欠くようになったとさえ思っていた。

彼女の精神を特色付けるのは、「反抗」、「反感」、「敬意を欠く」。
シャルル・ボードレールは出版直後の『ボヴァリー夫人』を論じながら、「黒い怒り」という言葉を使った。全てのものに怒りをぶつける気質こそ、エンマのエネルギーの源に他ならない。
『悪の華』の詩人が、シェークスピアのマクベス夫人を援用し、ボヴァリー夫人には男性の血が流れているとし、力強く、常に何かを求め、夢見がちな姿勢から、「ヒステリー」という言葉を使ったのも、全ては「黒い怒り」に由来する。
そして、その怒りの理由は、彼女が「理想を追い求めている」からだと、ボードレールは結論付ける。
フロベールは、その書評への礼状をボードレールに送り、「あなたは作品の奥義の中に入ってくださいました。私の脳髄があなたの脳髄であるかのようにです。「完璧に」理解し、感じてくださいました。」と書き記している。
では、エンマの追い求める「理想」とは何か?
フロベールはそれを語り手として延々と説明するのではなく、「教会が好きなのは花のため」だとする。
彼女が好きなもの、つまり追い求めるものは「花」。
教会が信仰の場としても、彼女はそこに信仰ではなく「美」を見る。それが「理想」なのだ。
「ロマンスの歌詞」も「情熱的な興奮」も、「美」の属性と見なすことができる。
エンマの「反抗」は、「現実的」な社会的・道徳的・宗教的規範にだけではなく、ロマン主義的な「熱狂」にも向かう。もはやどちらにも「美」は見いだせない。
だからこそ、「黒い怒り」は彼女に「花」を愛させ、「情熱的な興奮」を希求させる。
ボヴァリー夫人となったエンマが、夫シャルルに常に不満を感じ、レオンとロマン主義的な情熱を共有してみたり、ロドルフの甘い言葉に身を委ねるのも、どこにいったとしても手にすることができない「花」を求めているからに他ならない。

市民道徳からすれば、レオンやロドルフとの関係は不倫であり、断罪すべき行為を犯していると非難される。そうした倫理観が支配する近代市民社会では、何よりも「資本」が優先され、「美」を夢見ていたらたちまち置いていかれてしまう。
恋愛に関しては言えば、文学において、文学で不倫をテーマにすることは平凡なこと。恋愛の基本には三角関係があり、結婚する二人にもう一人の人間が加わり、障害ができる。生涯が大きければ大きいほど、情熱は激しくなり、物語として興味を引くものになる。
しかも、絵画で裸体を描く伝統があるのと同様、現実世界でも不倫はしばしば起こる。
そうした中で『ボヴァリー夫人』が公序良俗を犯すものとして裁判にかけられたとしたら、それは不倫自体の問題ではなく、エンマの発散する強烈なエネルギーが強い印象を与え、読者を魅了したからに違いない。

その魅力は、不倫の心理分析などから発するのではなく、ロマン主義的魂が現実社会の中で美を追い求めるエネルギーの強烈さから生み出される。
エンマの「反抗」や「反感」の強さは、その具体的な現れに他ならない。
ボードレールが「ヒステリー」と言うほどの激しい欲求。「ボヴァリー夫人は一人の男性」という表現も、同じことを意味している。
そのエネルギーの動力は、プラトニスムにおける「愛」。地上の人間を天上のイデアに運ぶのが「愛」。その「愛」が「美」を生み出す。
このように考えると、フロベールが『悪の華』に対して、「ロマン主義を刷新する」という言い方をした意味が理解できてくる。
ロマン主義はプラトニスムを踏襲し、現実とイデア界を二元論的に捉える。その上で、ここにないものに対するメランコリックな憧れが抒情的な美を生み出すという原理に基づいている。
それに対して、フロベールとボードレールは、二元論を捨て、現実世界にエネルギーを注ぐことで「美」を生み出そうとしたのだといえる。
ボードレールが、「現代生活(現実)の英雄(永遠)性」とか、「美は束の間でありながら永遠である」と表現したことは、現実=イデア界という一元論的世界観に基づく美の生成を意味している。
「花」を愛するエンマの気質が、近代市民社会を規定する倫理的、社会的、宗教的の規範に反抗する情熱を燃え上がらせ、醜を美に変える錬金術を作動させる。
彼女は19世紀前半のロマン主義時代のように、思い出や自然に夢の実現を求めるのではなく、彼女自身の生きる現実の中で「ロマンスの歌詞」を歌い、「今・ここ」を「美」としていくのだ。

読者の自由 読書の楽しみ

『ボヴァリー夫人』の中でフロベールが創造した「新しい現実」は、資本主義経済の中で自然選択が行われる近代市民社会であり、その中でエンマとシャルルを中心に数多くの人々がごく自然に日常生活を送っている。
小説の読者はその様子をあたかも現実世界であるかのようにたどっていくのだが、ただし、小説という枠組みがあるために、それぞれの出来事や事物に「意味」を見出そうとする。こう言ってよければ、全てを何かの暗示あるいは象徴として読み取ろうとする。
多くの場合は、エンマの性格と心理分析。
室内の様子や大規模な催し物の描写が、様々に関連付けられ、物語を理解するための隠された鍵として「発見」することもできる。
読者には、小説、つまりフロベールの言葉による建築を読み進み、自由に解釈し、意味を見つけ出す楽しみが許されている。

一つの例を紹介してみよう。
フロベールは小説の中で一度もエンマ・ボヴァリーとは書いていないので、「エンマ・ボヴァリー」の悲劇というフィクションが存在するのではない。だから一般論に惑わされず、フロベールの言葉をしっかりと読み説くことが必要。
そのように読んでみると、エンマはシャルルの行動を模倣、反復する傾向があり、二人は似た存在であることがわかる。シャルルが最初の結婚をしたも、エンマがシャルルと結婚するのも、親が経済的な理由から決めたもの。二人ともその結婚には満足しない。シャルルは結婚中にエンマに惹かれ、エンマは結婚中に他の男に惹かれる。さらに、シャルルは貧乏学生時代に寒さをしのぐために、部屋の壁を靴底で蹴って足を暖め、エンマは寒い中で馬車の出発を待ちながら、編上靴の底を中庭の石畳に打ちつけて、爪先のかじかむのをふせぐ。つまり二人は同じしぐさをする。
シャルルを愚鈍な夫と決めつけることも、薬剤師のオメを俗物の代表として蔑むことも、逆にシャルルの弱さに共感し、オメの俗物性を楽しむこともできる。
オメは停滞した村の成功者にすぎず、彼の野心などは大したことはない。それに対して、エンマに商品を売りつけた商人のルルは、最後には乗合馬車屋の経営者=資本家になる。真の成功者はルルだと、勝ち組の論理を都会と田舎にまで拡大する読み方もできる。
さらには単に不倫小説とか恋愛小説といった読み方をしてもいい。
様々な読み方が読者には許されているし、読者はその自由を享受しうる。
その読み方は、読者自身を映し出す鏡なのだ。

19世紀後半の文学作品は、現実を本物とし、その再現によって成り立つという伝統的な芸術観を捨て、作品の中の世界が本物として存在する芸術観へと転換した。
読者は、作品の裏にモデルを探す必要はなく、作品から出発して、自由な解釈をすることが許される。
その自由が読書の楽しみを作り出す。
『ボヴァリー夫人』は、そうした芸術観の転換点に位置している。
「ギュスターヴ・フロベール 『ボヴァリー夫人』 市民社会の生存競争とエンマの「黒い怒り」 新しい現実の創造 3/4」への1件のフィードバック