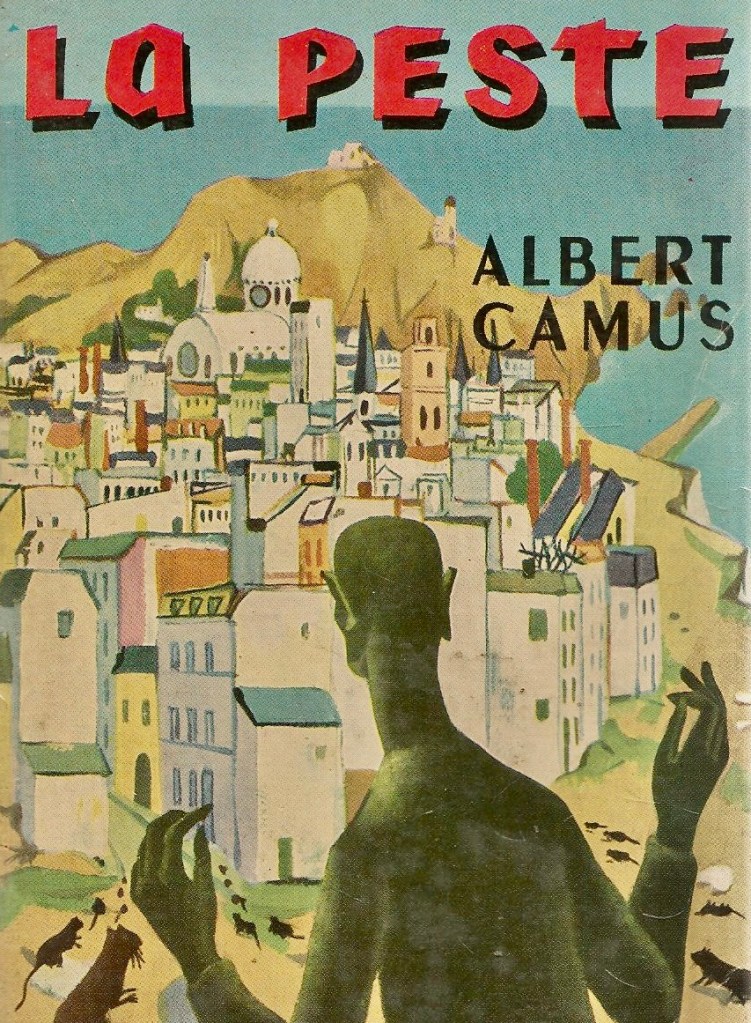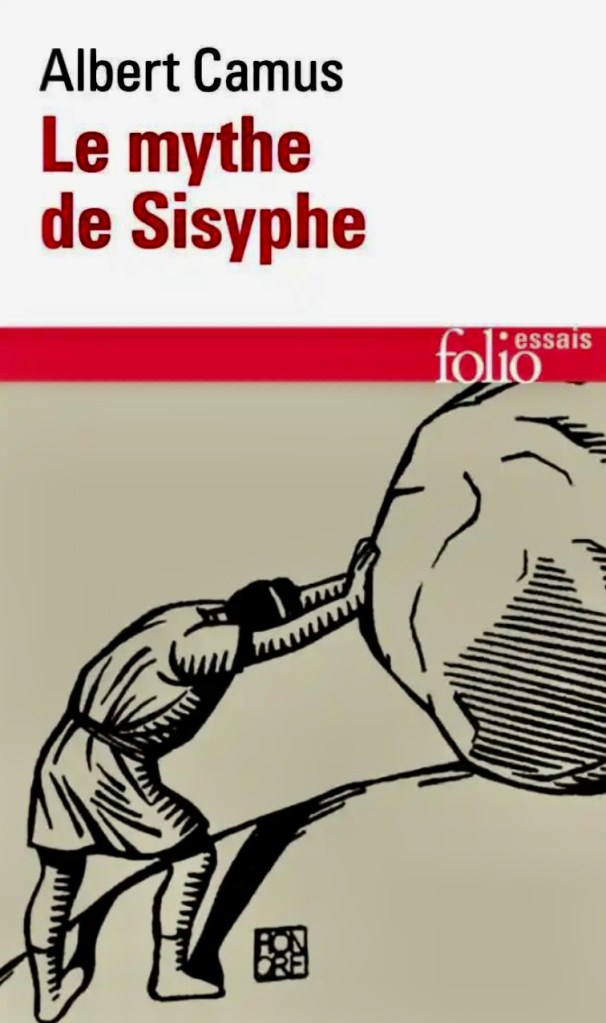
シーシュポスは、ギリシア神話の登場人物で、非常に賢いと同時に狡猾であるともされる。
彼は何度も神々を欺き、とりわけ、死の神タナトスを鎖で縛り人間の死を停止させたために、神々の激しい怒りを買ったエピソードが知られている。
そして、そうした神々に対する反抗のために捉えられ、地獄で罰を受けることになる。その罰とは、大きな岩を山の頂上まで運び上げるというもの。一旦頂上に近づくと岩は麓へと落下し、シーシュポスは再び岩を山頂まで運ばなければならない。そして、その往復が永遠に繰り返される。
アルベール・カミュはその古代ギリシア神話の登場人物を取り上げ、『シーシュポスの神話』と題された哲学的エセーの中で、「不条理(absurde)」という概念を中心にした思想を提示した。
シーシュポスは「不条理なヒーロー(le héros absurde)」なのだ。
不条理は人間の生存そのものであり、それは悲劇的なことだ。
しかし、その悲劇は悲劇だけでは終わらない。そのことは、エセーの最後が、「シーシュポスを幸福だと思い描かなければならない」という言葉で終わっていることでも示される。
ここでは、悲劇から幸福への転換がどのような思考によって可能になるのか探っていこう。

エセーは、シーシュポスの神話の概要を簡単に紹介することから始まる。
Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu’au sommet d’une montagne d’où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu’il n’est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir.
続きを読む