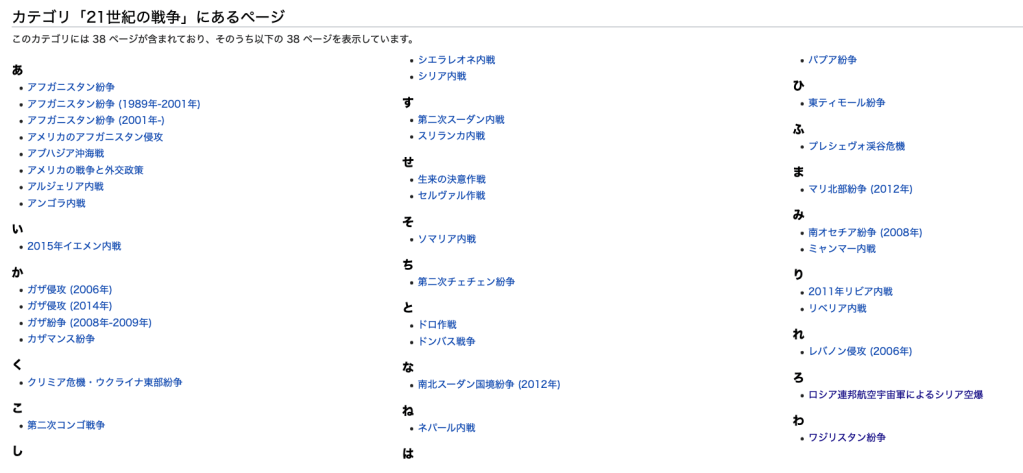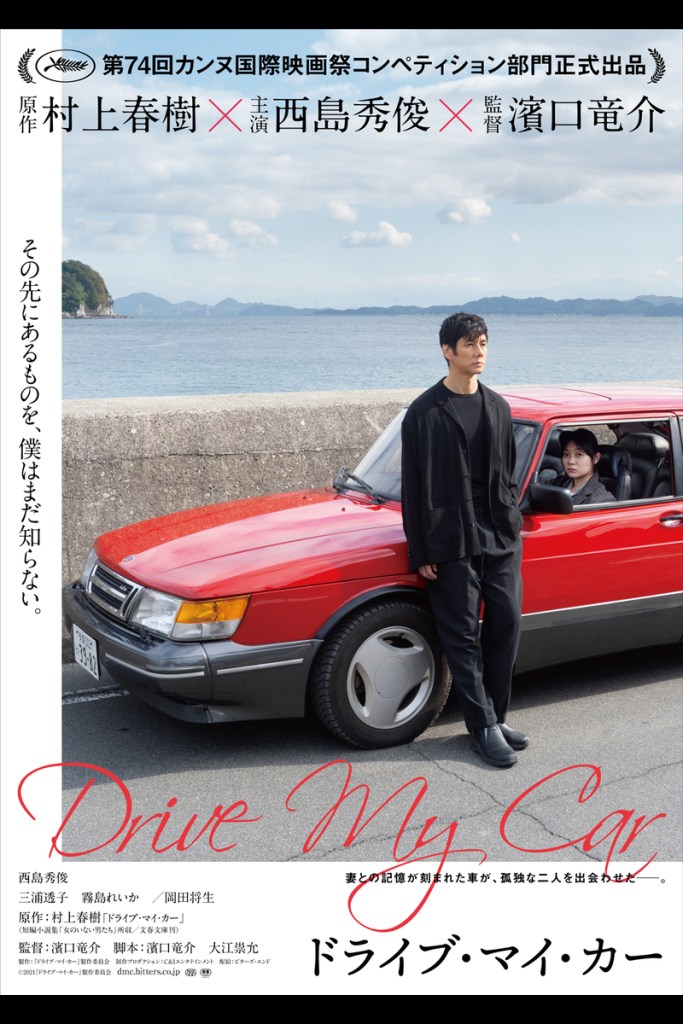ネット上では、「ネタバレあり」とか「ネタバレ注意」とかいうように、「ネタバレ」という言葉にしばしば出会う。
映画であれば、あらすじを最後まで語るとか、とりわけ最後に準備されている大どんでん返しをバラしてしまうと観客の楽しみが損なわれると考えられ、「ネタバレ注意」と言われることがある。
しかし、ふと振り返ってみると、好きな映画ならば、2度、3度と見ることはよくある。その場合には、ネタはバレている。でも楽しむことができる。
そんなことを考えながら、ネタバレについて考えてみよう。
出発点は、ビリー・ワイルダー監督の「情婦(原題:Witness for the Prosecution」)。
アガサ・クリスティの短編小説「検察側の証人」が原作で、最後の最後に大々どんでん返しがあり、本当に面白い。
そして、映画の最後に、次のクレジットが入る。
The management of this theater suggests that, for the greater entertainment of your friends who have not yet seen the picture, you will not divulge to anyone the secret of the ending of Witness for the Prosecution.
要するに、映画をまだ見ていない友だちが最大限に楽しめるように、映画の最後に置かれた秘密を漏らさないようにして下さい、という内容。
続きを読む →