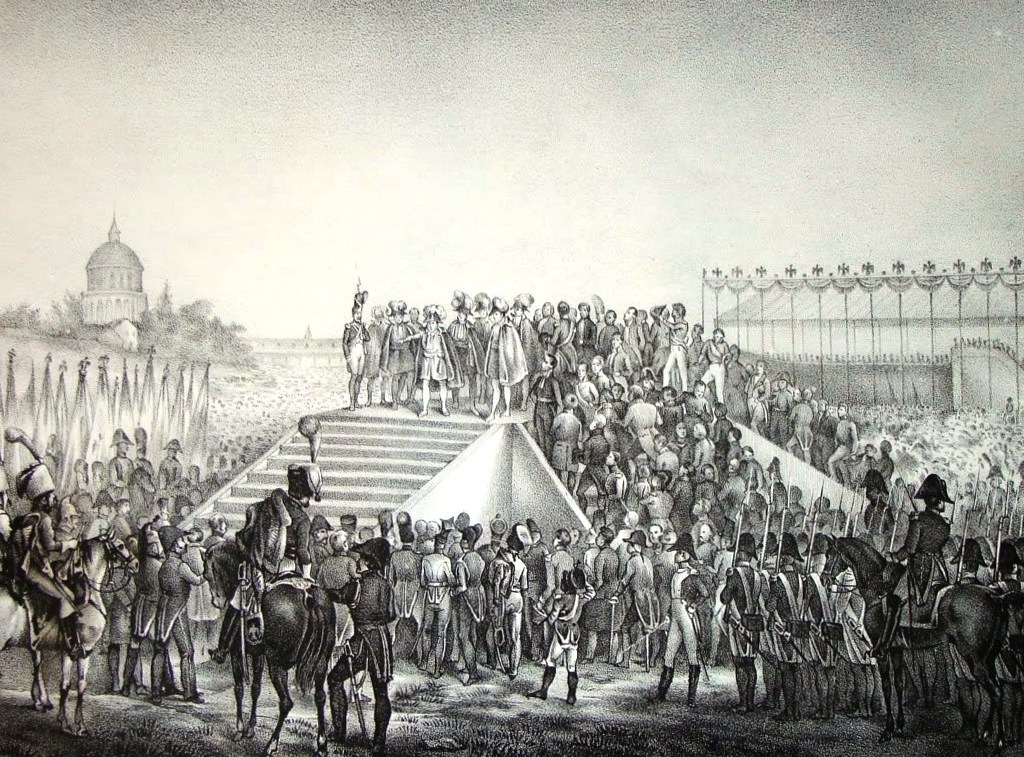第2章

しばらく後になり、私は彼女と別の町で出会った。そこには、長い間希望もなく愛し続けてきた、あの女性もいた。ある偶然から二人は知り合いになり、彼女は、おそらく何かの機会に、私を心の中から追放してしまった女性の心を、私に好意的になるように動かしてくれた。その結果、ある日、その女性の参加している場に私が居合わせた時、彼女がこちらにやって来て、手を差し出してくれるのを見た。その振る舞いと、会釈してくれた時の深く悲しげな眼差しを、どのように解釈すればいいのだろう? 私はそこに過去の許しを見たように思った。慈悲の籠もった神聖な話し方は、彼女が私に向けた何気ない言葉に、言いようのない価値を与えていた。ちょうど、それまでは世俗的だった愛の穏やかさに宗教的な何かが溶け込み、そこに永遠の性質を刻み込むように。

注:
一人の女性を世俗的で現実的、もう一人を近寄りがたい神聖な存在とすることは、現実とイデアに基づくプラトン的二元論の世界像を作り出すことにつながる。
ネルヴァルがそうした設定をしたのは、17−18世紀以降、合理主義・科学主義が支配的となった時代において、検証可能な現実世界を超える世界(イデア、永遠)を信じることが許されなくなっていたからに違いない。
そのことは、第1章の次の一節からも推測することができる。
「なんという狂気だろう。私を愛してくれない女性を、プラトニックな愛で、これほど愛するなんて。これは読書のせいだ。詩人たちが発明したことを真面目に受け取ってしまったのだ。今の時代のどこにでもいる女性を、ラウラやベアトリーチェにしてしまったのだ・・・。」
ラウラは、ルネサンス期のイタリアの詩人ペトラルカが愛を捧げた女性。ベアトリーチェは、ダンテが『新生』の中で愛を語った女性。彼らはごく普通の女性をミューズとして異次元の存在に変えた。
19世紀のネルヴァルが異次元とするのは、もはや天上のイデア界ではなく、人間の内面世界。そのことは、『オーレリア』の冒頭で、「私の精神の神秘の中で起こったこと」を綴る、としていることからも理解できる。
ネルヴァルが「狂気」の体験を描くことの意義が、こうした考察から理解できるだろう。