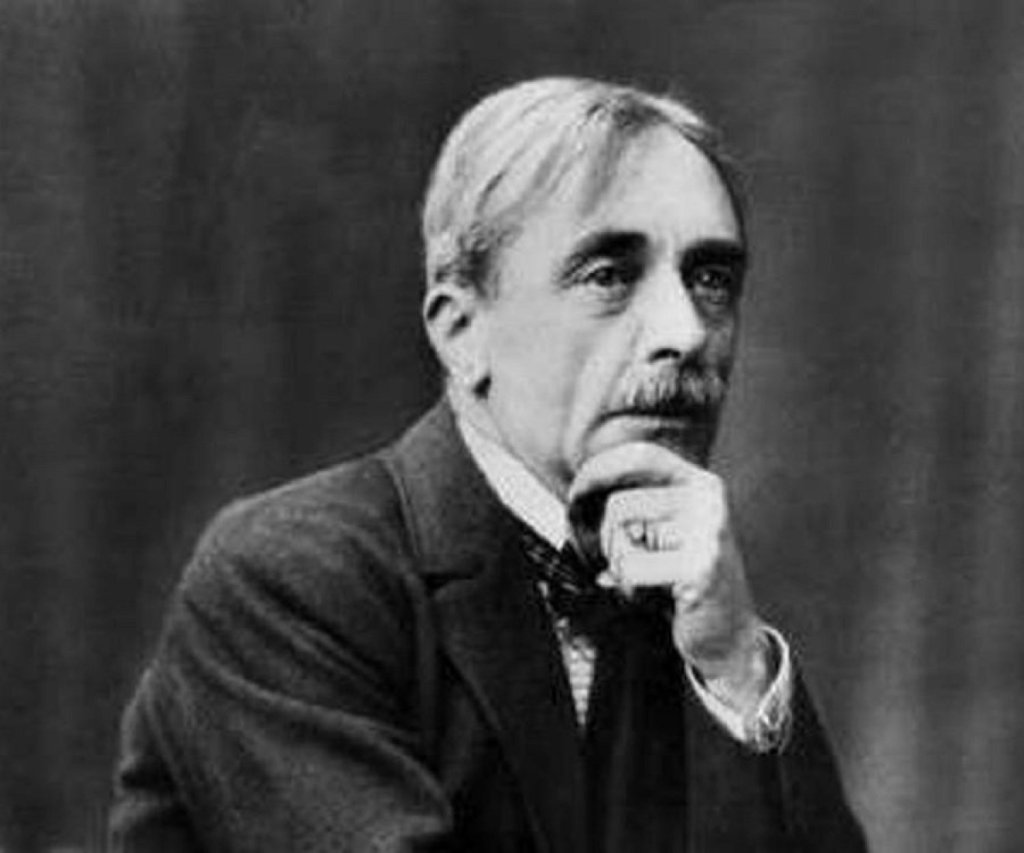ポール・ヴァレリーが詩のおいて最も重視しているのは、意味と音の連動だった。詩的言語のリズムやハーモニーが生み出す音楽は、単に耳に心地よく響くというだけではなく、日常的に用いられる言語の意味を解体し、より強く感性に働きかけ、精神の活動を活発にする。
言語には感情を動かす力があり、その力は、直接的に意味を伝える実際的な力と混ざり合っている。詩人の義務、仕事、役割は、動かし魅了する力、感情の働きや知的な感受性を刺戟するものを明らかにし、活動させることだ。それらは、通常の言語の使用の中では、ごく当たり前で表面的な生活において使われる記号やコミュニケーションの道具と混同されている。(「ボードレールの状況」)
私たちの日常生活では、言葉は相手に自分の考えや感情を伝えるために使われる。それに対して、詩的言語は「言語の中のもう一つの言語」となり、通常の言語使用では伝えられないものを「暗示」し、人を魔法にかけるような「魅惑」を生み出す。
続きを読む