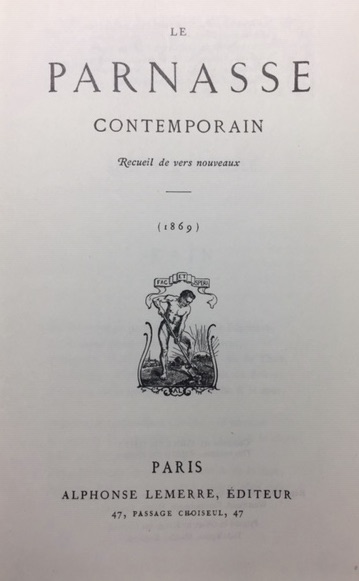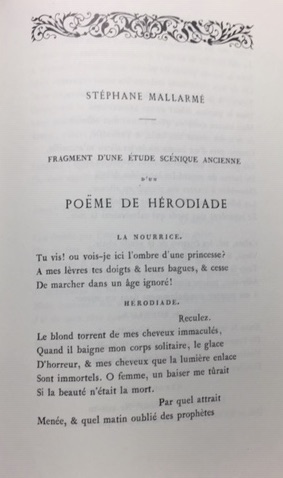日本の文化の中で「無」が重要な役割を果たすことはよく知られているが、「無」とは何なのか、そしてなぜ日本人が「無」にこれほど惹かれるのか、説明しようとしてもなかなかできない。
そうした中で、荘子の思想は重要なヒントを与えてくれる。
大変興味深いことに、8世紀末期に成立した日本最古の和歌集『万葉集』には、荘子受容の最初の例としてよく知られる歌がある。
心をし 無何有(むかう)の郷に 置きてあらば 藐孤射(はこや)の山を 見まく近けむ (巻16・3851番)
もし心を「無何有の郷」、つまり「何もなく、無為(むい)で作為(さくい)のない状態」に置くならば、「藐孤射の山」、つまり「仙人が住むとされる山」を見ることも近いだろう、とこの作者未詳の歌は詠っている。
現代の私たちも、無の状態になることが何かを成し遂げるときに最もよい方法だと言うことがあるが、それと同じことを、今から1300年以上も前の無名の歌人も詠っていたことになる。
そして、「無何有の郷」と「藐孤射の山」が、『荘子』の「逍遥遊(しょうようゆう)」篇で語られる挿話に出てくる固有名詞だということを知ると、日本人の心のあり方と荘子との関係に深さがはっきりと見えてくる。