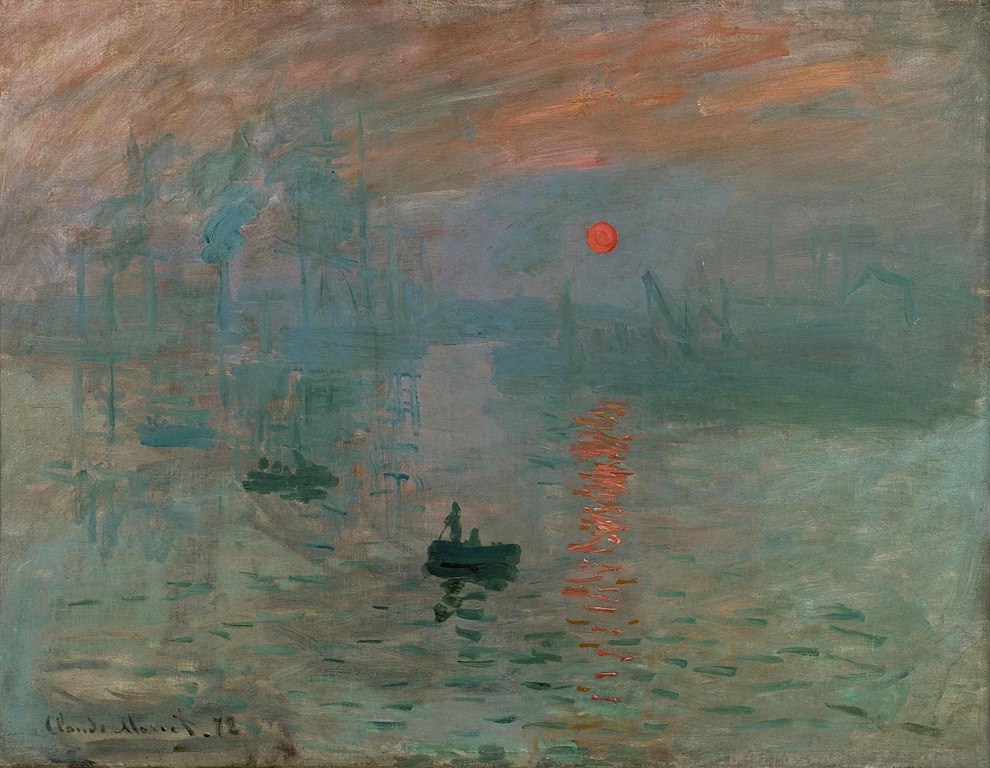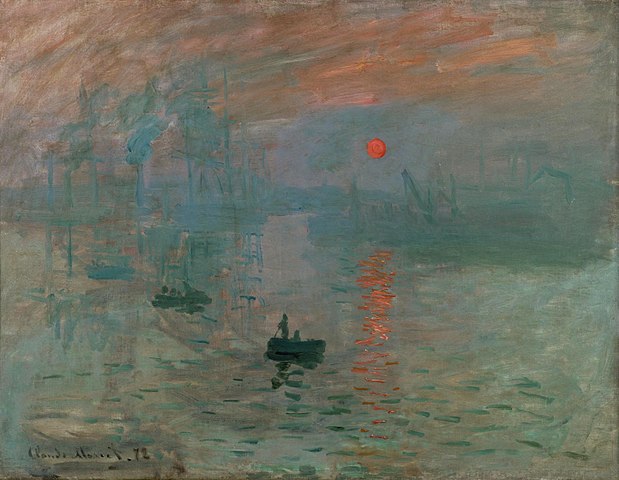
ポール・ヴェルレーヌを代表する『言葉のない歌曲集』が出版されたのは1874年。クロード・モネの「印象 日の出」が展示された、いわゆる第一回印象派展が開催されたのと同じ年だった。
この偶然は、ヴェルレーヌの詩が印象派の絵画と同じ種類の美を目指していることを示す、「意味ある偶然」だといえる。
彼らの新しさは、絵画、詩の言葉、ドビュシーなど音楽家であれば音楽によって、「印象」を表現しようとしたことだった。
私たちは「印象」という言葉を、普段何気なく使っている。第一印象がいい、印象が薄い、印象的な風景、等々。しかし、「印象」とは何かを考えることは少ない。
印象が生じるためには、二つの要素が必要になる。一つは、見たり聞いたりする人間。もう一つはその対象となるもの。
一人の人間が、ある対象を見たり聞いたり触ったりした時、心の中で感じるものが、印象と呼ばれる。
そこで注目したいのは、同じものに対しても、印象は人によって異なるだけではなく、場所の違いや時間の経過の中でも違う可能性があるということ。
印象派の画家たちが、同じ対象を何度も描いたのは、時間の経過に従って光は絶えず変化し、その当たり方によって違って見えるから他ならない。


そうした視点から考え直してみると、「印象」とは、五感が捉える対象とその刺激を受け入れる心、つまり外界と内面の共同作業から生まれる不安定な感覚であることがわかる。
そのため、「印象」に基づいて表現された世界像は、現実に忠実な写実的な映像でもなく、現実の核を欠いた空想的な映像でもない。
こう言ってよければ、それ自体で、一つの自立した世界を作り出している。
モネのサン・ラザール駅は、現実の駅を再現しているのではなく、1枚1枚が、それぞれのサン・ラザール駅なのだ。
ヴェルレーヌの「巷に雨が降るごとく」(掘口大學訳)でも、同じことが言える。
雨が降るのは外界だが、「同時に」、心の中にも涙が降る。というか、雨が降るのは、外界と心が一つになった「印象」の中なのだ。
心の中に涙が降る。
街に雨が降るように。
私の心を貫き通す
この物憂さは何だろう。 (「忘れられたアリエッタ 3」)